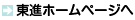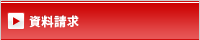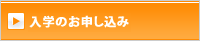ブログ
2024年 7月 15日 議論、していますか?
こんにちは!担任助手1年の徳丸です。
7月も中旬になりましたが、春から続けてきた受講も終わりが見え、過去問も始める頃でしょうか。
あえてこのタイミングで質問しますが、
授業や解説を聞いてただ分かった気になっている部分はありませんか?
先生方は授業がうまいので、授業についていけば分かった気にはなれます。
ですが、分かったつもりのことを問題で問われて答えられないことがあるのは、
それを自分でよく考えることが不足しているからです。
同じ授業を受けたはずなのにテストなどで出来不出来が分かれるのもこれが原因です。
では、どうすればよいのか?
キーワードは「議論」だと思います。
ここで言う「議論」は自分との議論、友達や先生との議論、問題との議論など広い意味で使っています。
議論を重ねて理解の穴を一つ一つ埋めていくことで積み上げてきた基礎はより盤石となり、その上に志望校対策の効果がどんどん積みあがっていきます。
目安として、授業や問題について先生のように説明できるようになることを目標にすると良いと思います。
では具体的にどう「議論」するのか、先ほど挙げた3つの議論についてそれぞれ説明してみます。
<自分との議論>
分かった気がしたことを自分の中のなぜなぜ坊やに説明するイメージです。
「なんでその式変形をしようと思ったの?」
「なんで本文のここを根拠にしたの?」
この繰り返しで、思考を言語化して頭を整理しつつ、なんだか曖昧だなあと思うところを潰していけば、かなりの理解度に到達できます。
紙に書き出すのもいいと思います。
<友達との議論>
勉強したことを友達と議論し合うのはとても有益です。
分からない所を質問し合うのもよし、一緒に問題を解くのもよし。
他者の存在が、自分一人では気づけていなかった理解の穴に光を当ててくれます。
自分の考えを説明する中でもし詰まったら、そこが補強すべき弱点です。
友達の説明を聞けば、それまで持っていなかったアプローチの仕方が手に入るかもしれません。
でも雑談に流れないようには注意してくださいね!
<問題との議論>
やることは問題演習ですが、一度問題を<自分との議論>のなぜなぜ坊やや、<友達との議論>での友達を問題に置き換えて考えてみてください。
問題は”ある事柄”について理解を深めるのに役立つ「なぜ?」を提示してくれているのです(文字通り”問題”ですね)。
ここからは自分や友達との議論と同じです。
説明してあげるつもりで解き、詰まったところは改めて補強してください。
さらに踏み込んで、”ある事柄”とは何なのか?なんて考えていると出題者の意図まで見えてくるかもしれません。
長々と書いてしまいましたが、この文章のメッセージは
「演習に入る今だからこそ、日々の勉強に”議論”を取り入れてみてほしい」
ということです。頑張ってください!!
2024年 7月 12日 夏は受験の天王山
こんにちは、担任助手の坂本龍之介です。
7月に入り、夏がやってきました。皆さんは夏、好きですか?
暑くて最高ですよね。
しかし、そんな素敵な季節に似つかわしくないこんな言葉があります。
「夏は受験の天王山」
耳にタコができるほど聞いてうんざりしている人もいるかも知れませんが、
この言葉を聞いて自動的に目を背ける前に、この言葉の正体について少し考えてみましょう。
「天王山」とは、
羽柴秀吉が明智光秀を破った山崎の戦いが起こった場所で、
そのことから「勝敗の分かれ道」という意味で使われるようになったそうです。
では次に、
なぜ取り立てて夏が名指しで「天王山」扱いされているのか、です。
それは、夏に「変化」があるからだと思います。
高校生であれば、7-8月に夏休みが始まります。
そして浪人生は7-8月に通期講習が一旦途切れて、夏期講習に入ります。
どちらの場合でも、生活のルーティンに変化が入ります。
春からずっと続けてきた習慣が突然終わり、
夏休みに入る高校生にとっては【時間が増大して大成長する期間】となり、
浪人生にとっては【平時の学習時間に自由が生まれて】気がゆるんでしまう、
そうした【変化が訪れる】タイミングが夏なのでしょう。
「勝敗の分かれ道」と仰々しい言い方をされるとちょっと気が引けますが、
ただ単に「気がゆるみやすい時期」だと考えれば、少しは気持ちが楽になるのではないでしょうか。
ルーティンの変化に緩むことなく、頑張ってください!
2024年 7月 10日 鳥瞰図
こんにちは!担任助手の島村です。
最近は暑くなってきて、室内と屋外との寒暖差にやられるという人も多いのではないでしょうか。
浪人生にとって体は資本ですのでくれぐれも風邪をひくことがないようにしましょう!
もう七月ということでそろそろ浪人にも慣れてきて勉強することが当たり前の生活になってきたのではないでしょうか?
私も浪人を経験していますが浪人生は本当に偉いと思います。
志望校に合格するという自分の目標を達成するために、しっかりとその目標に向かって日々勉強しているのですから本当に偉いと思います。
また、同世代の現役の人たちは大学生活を満喫しているわけですからなおさら偉いと思います。
一日一日勉強が終わったら自分をほめてあげてほしいです。
恥ずかしいですが、自分は一日勉強を頑張る自分をとても偉いと思っていました。
このブログを読んでいる人の中にも同じような考え方を持っている人もいるのではないでしょうか。
ですが、ここで一回考えてみてほしいです。
確かに浪人生はとても偉いと思います。
ですが、その浪人は誰のおかげでできているのでしょうか。
浪人生活での成績向上は誰のサポートがあったからでしょうか。
これをこの浪人に慣れてきた頃に考え直してほしいです。
日々努力する自分に慢心して傲慢になっていませんか?
この浪人に慣れてきた頃に、まずは日々の生活をサポートしてくれている保護者や担任の方などに感謝して一回謙虚になりましょう。
そうすればまた初心に帰るができ、もう一度目標に向かって頑張れるのではないでしょうか。
今一度自分の生活を振り返ってみてください。
最期まで読んでいただきありがとうございました。
頑張って夏を乗り越えましょう!
2024年 7月 5日 やる気があれば勉強できる?
こんにちは。担任助手3年の大島です。
勉強しなければならないけど中々やる気が出ないそこのあなた!!
是非最後まで読んでみてください!
まず、勉強をする上で第一関門となるのが、勉強をスタートするまでだと思います。
SNS、テレビがいいところ、ソファーから動きたくないなど障壁が山ほどあり、勉強を始めるまでのハードルが一番高い場面だと思います。
そんな時は3秒以内にとりあえず机に座ってみることです。
なぜ3秒かというと、人間は3秒のうちに言い訳を作ってしまうからです。
言い訳を考えつく前に行動する必要があります。
また、脳には側坐核という部位があり、やる気や意欲と深く関わっていると言われています。側坐核は行動をすることで機能し始めます。
そのため、行動することで側坐核が働き、やる気や意欲が出てきます。
つまり人間は、
「意欲があるからやる」のではなく、「やったからやる気になる」のです。
次に、勉強をしていて誘惑になるのがスマホだと思います。
ちょっと息抜きにスマホを触ってて、気がついたらもうこんな時間…という経験をした人もいるのではないでしょうか。
スマホを触るきっかけは多く、アラームを止めたり、通知音など日常にあふれています。
また、スマホを触ると快楽物資であるドーパミンが放出され、スマホ依存を引き起こし、結果的にスマホをやめたくてもやめられない状況に陥ります。
ならばスマホを触るきっかけを作らせないことです。
そのためには通知音やスマホの電源を消す、視界から排除するのが効果的です。スマホは目と手の届く範囲に置かず、預かってもらったり、別の部屋に置くなどして、できるだけ遠くに置いておきましょう。
以上が勉強をはかどらせるためのちょっとしたアドバイスです。
みなさんの参考になれば幸いです。1日1日を大切に一緒に頑張っていきましょう!最後までお読みいただきありがとうございました。
2024年 7月 4日 受験に「人付き合い」は必要?
こんにちは。担任助手2年の黒田です。
最近、またコロナウィルスが流行ってきているようですから、くれぐれも気をつけましょう。
さて、4月・5月・そして6月が終わりに近づいてきましたが、皆さんはよく話す人や仲の良い人はできましたでしょうか?
私は生来、対人コミュニケーションというもの全般が非常に苦手なタイプでして、当然浪人でもその特質が変わることはなく、7月ほどまで誰ともまともに話したことがありませんでした。昼休みの教室の雰囲気に耐えきれず、いつも昼は校舎外へ赴き一人で食べていました。
「第一志望を合格する上で、人と付き合うことはマイナスにしかならない」と私は思っていたのです。確かにそういった側面が無いとは言いきれません。けれど、それ以上に人とコミュニケーションをとることの利点は多いと私は思います。
最終的に、私の対人コミュニケーションの軸となったのは、同じチームミーティングのメンバーでした。最初の数ヶ月はチームミーティングに出席はするものの、会話にはほぼ混じらず、1人で下を向いて課題を熟すというのが殆どでしたが、メンバーの一人から食事に誘われたのを皮切りに、夏に入った辺りから少しずつ彼らと会話をするようになっていきました。
元々、同じ大学帯を志望する仲間だったこともあり、当然ともいうべきか過去問や勉強法などについて話題は尽きず、そのうちに模試の分析を共有したり、互いの悪い点を指摘したりと高め合うことができ、登校する際のモチベーションや日々の良い刺激になりました。
しかし、最大のメリットは競争相手を見つけることができたという点だと思っています。受験は個人戦です。それでも、自分がどれくらい勉強ができているのか。周りはどれほどやっているのか不安になることはあるでしょう。
私も例に漏れずその質でした。そうした情報を互いに共有することで、普段の受講ペースは勿論、模試の点数やライブ授業での小テストの点に至るまで何れの場合においても絶対に抜かれまいと勉強をすることに熱が入りました。
また、自分と近い実力をもつ人を見つけることは、「そろそろ家に帰りたいけど、あいつはまだやってるし、もう少し頑張ろう」というように自分を引き締めることにも一役買うでしょう。
もちろん、相手に勝つことばかりに夢中になってしまい、本来の自分の目標から外れてしまったり、互いの足を引っ張りあってしまうような関係にならないよう気をつけなければなりません。逆に、仲良くなり過ぎて勉強に集中できなくなってしまったら本末転倒です。
節度を持って他の人達と上手く付き合ってみてはいかがでしょうか?
競い合うのは存外楽しいものです。
そう、受験自体は個人戦ですが、受験までの過程は団体戦なのです。