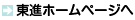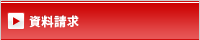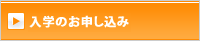ブログ
2018年 10月 7日 早稲田大学(文学部・文化構想学部)について
こんにちは。早稲田大学文学部一年、佐藤恒太です。
今日のブログのテーマは8月のSHRで扱った、早稲田大学についてです。
まずは早稲田での学びについてです。
自分は文学部に所属しているのですが、早稲田の文学部では週4で第2外国語の勉強をしています(1年次)。
また、レポートや論文を書くための練習をする必修授業もあります。
受験生のときにはあまりイメージできていなかったレポートや論文について理解するとともに、書き方も身につけることができました。
また自由に取れる授業では、ジェンダーの問題について先生と意見交換をする授業や、少女マンガの原作と実写化を比較分析する授業、シェイクスピアと現代の繋がりについて考える授業などを取っていました。
元々自分は文学部志望でこのような勉強がしたかったので、満足しています。
皆さんも自分のやりたい勉強ができる大学、学部を選べるようにしてください。そして、その志望校に向かって日々着々と力をつけていきましょう!
そして、早稲田での学生生活についてです。
学生生活については十人十色でその人次第です。
サークル、資格の勉強、バイト、個人的な趣味等々
自分は東進で担任助手として働いている傍らで、大学のサークルでミュージカルをしています。週に3回ほど練習をしています。
早稲田には(もちろん他の大学にも)沢山のジャンルのサークルがあります。
大学生になったら自分に合ったサークルが必ずあるはずなのでそのサークルを見つけられると良いですね。
早稲田の紹介というか自分の紹介っぽくなってしまいましたが、これを読んで皆さんが早稲田にいくモチベーションを上げてもらえたら幸いです。
これで今回のブログは以上です。最後まで読んでいただきありがとうございます。
担任助手 佐藤
2018年 10月 5日 過去問演習のスリーステップ
こんにちは、東京工業大学3年の後岡です。
季節の変わり目でだんだんと涼しくなってきましたね。
体調にお気を付けください。
さて、今回は過去問をどう活用するかについて書こうと思います。
まずは、解く。
私はできる限り本番に近い形で解いていました。
例えば、本番で午前中に実施されるものは午前中に解いたり、仕切られているブース席でなくひらけている教室で解いたり。
そして当たり前のことですが、集中して解くこと。本番だったらどうするか、ということを念頭に置いて解くといいと思います。
続いて、復習。
「1度見た問題は、今後絶対落とさない」これが復習における重要なポイントです。
間違えた問題はもちろんですが、正解していた問題の解説も必ず読みましょう。知識の確認ができますし、もしかしたら新しい発見があるかもしれません。
私は、間違えた問題に関しては解きなおしていました。正解した問題も解きたかったのですが、本番までの残り時間を考えたときに、省略せざるを得ませんでした。合格するために今何をすべきかを考えながら勉強しましょう。
そして、2回目を解く。
1回目の復習から最低でも1週間はあけて解きましょう。復習がしっかりできているなら自ずと満点です。ただ、これがなかなか難しかったりします。詰めの甘さというやつです。ここで見つけた詰めの余地をしっかり学習しましょう。
以上が、私がやっていた過去問の活用法です。皆さんもぜひ試してください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
それではまた次回。
2018年 10月 3日 “センター対策いつから始める?”問題
担任助手2年の松澤です!ライブ授業紹介以来の投稿となりますね。
最近は秋雨前線と度重なる台風の影響で連日雨が続き、なかなか気分が乗ってこない嫌な時期だなぁと感じております。いつの間にか気温の方も夏に比べて10度近く低下しているので、生徒の皆さんは体調を崩さないように気を付けてくださいね。
本題に移りましょう。グループ・ミーティングや質問相談などで、生徒と話しているとたびたび、
「センター対策っていつから始めればいいですか?」
といったようなことを尋ねられます。この疑問に対する私なりの答えを以下で示します。
が、その前に一言。この手の問いを真剣に投げかけてくる人は大抵、直近に受験したセンター試験型の模試などの結果が悪く、目標と現状との差に絶望し、早くセンター対策を始めなきゃと不必要に焦っているだけな感じがします。該当するなぁと感じる人は、もう一度冷静に現状を分析し直し、早急な対策が本当に必要かどうかよく考えてみてください。
さて、いつ始めるべきかの問題ですね。
もちろんこれは、現状の実力、志望校のボーダーラインor足切り点、使用する科目数、配点に対するセンター試験の点の比率、センター利用、など様々な要因によって人それぞれ変わってきます。しかし、旧帝大、医学部、早慶などの難関大を目指す人であれば、本格的な対策は本番の1~2カ月前から始めれば十分間に合います。(私は12月のセンター試験本番レベル模試の翌日ぐらいから始めました。)
ここで言う「本格的な対策」の状態というのは、センター後に控える国公立二次試験や私大入試を見据えた勉強から、センター試験だけを見据えた勉強にシフトした状態のことを示します。センターでしか使わない科目や、記述型練習だけではどうしても得点が伸びない科目や分野などがある人は、それらに限って早期から策を講じるのは全然アリです。(私自身、センターでしか使わなかった地理Bや、模試での得点が不安定だった古文・漢文に関しては、10月頃から過去問演習や大問別演習などをこなしながら知識の復習を始めていました。)
そもそもセンター試験の対策をガチガチに固めるメリットはあまりないです。なぜなら、
①センター試験を解くのに必要とされる知識・発想のほとんどは二次試験の勉強をしていれば事足りる
②あまり早い時期にセンター対策を始めても、記述練習の時間を減らしてしまうことになるだけ
③二次試験よりもレベルが低いセンター試験のレベルに慣れすぎてしまう
④いくらセンター型の演習を積んでも、基礎事項(知識・計算・解法・スピード)が備わっていなければ、点数が大きく向上することはない
⑤難関大ではセンター試験の配点は低い(ことが多い)
などの理由からです。
また、本格的な対策としてやれることは、本当にセンター特化で局所的なものばかりだと思います。それゆえ、長い時間は必要ありませんし、むしろ、長い時間を割くべきでありません。(過去問演習以外で私がやっていた本格的な対策は、センター試験特有の出題形式に慣熟する、副教科の知識を詰め切る、解く順番を最適化する、メモの書き方を研究する、見直しの仕方を研究する、マークミスをチェックするタイミングを設ける、マークミスをしない工夫をする、パニックになったときの回復法を考える、新形式を予測する…などでした。)
以上を踏まえれば、ギリギリまで二次試験や私大入試を想定した勉強をし続け、本番直前でセンター試験特化型の勉強を集中的にやるのが一般的な大学合格への道として最も効率的だろうというのが結論です。そのギリギリをどこまで遅くまでもってこれるかは、皆さん次第ですね。
長くなりましたが、読んで下さりありがとうございました。いろいろ考えてみてください。また、次のブログでお会いしましょう。
担任助手 松澤
2018年 10月 1日 初めての過去問分析(私立向け)
お久しぶりです!担任助手2年の長谷川です。
最近は雨続きですね・・・。
なんだか気分も上がらない・・・、なんて言っていたいところですが、過去問演習に入り始めている今は日々の勉強内容が変わっていく時期なので、道筋を見失ってペースが乱れないよう、気を引き締めていきましょう。
本日のテーマは、先に触れた過去問の、“分析”についてです。
新宿本科では、分析分析と繰り返し言われていると思いますが、「分析って具体的に何をやればいいか分からない・・・」なんて声を聞くこともしばしばです。そこで、あくまで1つのやり方ではありますが、初期の段階でおすすめするやり方を書いて行こうと思います。
まず確認するべきことは、簡単に言ってしまうと、「自分が今までやってきた勉強や教材の内容でどれだけの問題が解けるか」ということです。
というのも、新宿本科で日々勉強に打ち込んできた生徒のみなさんは、この時期には入試問題を解く上で必要になる学力の土台の部分は、主要科目についてはほぼ学習が終わっている段階かと思います(土台が完成している、と言っているわけではなく、あとは同じ内容の復習や演習を繰り返すことで完成度を上げていく段階、ということです)。
そこで実際に過去問を解いてみると、もちろん問題の構成や特徴、解答根拠を拾ってくる範囲など分からないことが多いので、最初から高得点を取ることは困難です。しかし、解説を参考にしながら丁寧に分析してみると、解けなかった問題についても、意外と今までやってきたことを少し応用させた程度であったり、着眼点さえ分かっていれば解ける問題であったりすることが多いです。
自分の経験を例に挙げて少し書くと、世間一般で言う夏休みが終わったタイミングで早慶の過去問を解いて分析してみたところ、
英語:知らない単語はあるが、設問を解く上では意外と関係ないものも多い。多くの問題が下線部の前後の文脈が取れていさえすれば解ける。
指示語の問題が多く、本文を読解する際には指示語が何を指しているかを意識しながら読むべき。英作文は単に演習不足。
時間配分については、設問が本文の前から順番に作られているため、「先に設問を一つ見てから本文を読解することを繰り返す」のが一番効率がいい。最後の設問の内容一致は全文を通しての問題で解答に時間がかかるため、パッと見で分からなければ飛ばしてしまい、他の大問を全て解いてから余裕があれば解く。
→特別新しい勉強が必要という訳ではない。日常学習の時から、上に挙げた、過去問を解くときと同じ着眼点(解答の順番、指示語の意識、設問前後の文脈把握など)をもって解く。
日本史:一問一答的な語句知識だけだと選択肢が切れない問題が多く、語句の周辺知識(例:東進太郎は、○○時代の□□戦争後の不況下で△△会社を設立して、日本の経済発展に尽力した人物だ。)まで整理されていないと解けない。
語句の選択問題は、その語句が関わる時代に着目すれば2択までは絞れる。
教科書と一問一答に無い知識が必要な難問を全て排除しても8割は取れる。残りの2割も、消去法などを使えば絶対に解けないという訳ではない。
→今までの勉強で扱った内容の中で、知識の穴を無くすことと、語句の内容、周辺知識を教科書、ノートを使って整理していくことを意識して勉強する。
知識のインプットだけでなく、演習を積んでその都度知識の整理を行う。史料対策を除けば、新しく教材を増やす必要は無い。
という感じで、
①新しい勉強(内容)を取り入れる必要はあまりない。
②今までの学習内容の定着度を上げると同時に、知識の穴を見つけ、無くしていくこと。
③着目すべき点や、解答の導き方や解く順番と言った戦略を意識して演習を積むこと。
大まかにこの3点を意識すべきだということが分かりました。
何より、今までの学習内容で間違っていなかったという安心感と、今までの内容の完成度を高めていけば十分に合格できる、という自信を持てたことが大きかったと感じます。
もちろん上に挙げたのは分析の一部に過ぎませんし、やり方は人それぞれです。自分の課題が明確で、やるべきことも分かっている人もいれば、何が問題なのかもよく分かっていない人もいると思います。また、分析をしたところで、「ではどうしていくか?」「何を意識して勉強していくか?」などという、「これから」の部分が明確になっていないと、ただ時間を浪費してやった気になっただけになってしまいがちです。各々自分の現状や性格、傾向に合った分析を行い、確実に日々の学習や次の過去問演習に活かしていってください。
長くなりましたが、本日は以上です。
最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました!少しでも役に立てば幸いです。
それではまた!
2018年 9月 29日 商学部とは~SHR実施内容~
こんにちは。
早稲田大学商学部の粕谷です。お久しぶりですね。
この夏、校舎でSHRを行ったので、今回のブログはその内容について書いていきたいと思います。
今回僕が行ったSHRでは、経済学部、経営学部、そして商学部。それぞれの違いは何かを説明しました。
まずは経済学部。
経済学部では名前の通り経済学を中心に学びます。経済とは簡単に言えば、目には見えないモノとお金のやり取りです。このやり取りを理論化したものを学んでいきます。
次に経営学部。
この学部では経営に必要な能力を培うための学問を学びます。経営学はもちろん、経済学(経営者として経済についての最低理解は必要ですよね。)、統計学、ビジネス法等を学びます。
最後に商学部。
経営学部が経営に必要な能力を培うための学部であったら、商学部はビジネスを行う上で必要なことを学ぶ学部です。経済学、経営学、会計学、マーケティング、金融、保険、ビジネス法等を学びます。
イメージとしては、経済学部+経営学部+α=商学部です。
僕は商学部なので、商学部で学ぶ学問はもちろん、経済学、経営学も学びましたが、どの学問もとても奥が深く、学び概のあるものでした。
皆さんも大学に入ったら、必修科目かそうでないか問わず学んでみたらいかがでしょうか。