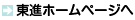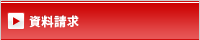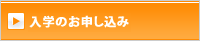ブログ
2018年 11月 21日 今時期からのメンタルの保ち方~袴田~
こんにちは、担任助手4年の袴田麻畝です。
寒い日が続きますが、体調管理はしっかりできているでしょうか?
さて、今回のテーマは「メンタルの保ち方」です。
試験が近づくにつれて、不安になったり、ネガティブなことを考えたりする人もいるかもしれませんが、それは今まで一生懸命勉強してきた人が抱く悩みだと思います。なので、今不安になっている受験生は勉強している証拠!だと私は言いたいです。
でも、不安のままでは勉強も手につかないと思うので、私なりのメンタルの保ち方を紹介していきます。
①模試の分析をする
模試分析なんて当たり前!と思うかもしれませんが、これは意外とメンタルの保つ上でも重要です。
「模試の結果に左右されるな」と何度も言われると思いますが、模試の結果を受け止めて、反省すべきことは反省して次につなげることは大切です。しかし、結果だけを鵜呑みにして、変に自信を持ったり、逆に落胆したりする必要はありません。
一番重要なのは、「模試を受けた後どう勉強していくか」です。
模試分析をしていれば、自ずと何を勉強していくかが明確になりますし、どんな結果であっても切り替えて勉強していけると思います。
②目的を明確にする
「なぜ勉強しているのか、なぜ志望校に合格したいのか」
この問いを自分に投げ続けることが、根本にあると思います。
ここで、どんな人であれ突きつめていけば、結局たどり着く先は「勉強する」だったりします。日々、勉強に取り組む理由を忘れないことで、途中メンタルにブレが生じても、メンタルを持ち直すきっかけになると思います。
また、不安とは逆に油断も生まれてしまうかもしれません。
受験勉強は自分との闘いで辛いことも多いと思います。
特に国立大学受験者は科目数も多いので、なんで毎日こんなに勉強しなきゃいけないのかと思うときもあるでしょう。
センター試験まで2か月弱、2次試験まで約3ヶ月。焦りも出始めている時期かと思いますが、その一方で「まだ大丈夫」という思いから、「今日くらいは少し休んでもいいかな」という魔が生じることもあるでしょう。油断こそ最大の敵だと思います、1点目の繰り返しになりますが、結果が良かった模試こそ注意して、不安だったけど解けた問題がなかったか確認しましょう。
私は本科生時代、浪人を決める前に「どんな結果であっても、最後までやり切る」と心に決めていました。そう思えたのも、大学でどんな勉強をしたいか、将来どんな職業に就きたいかが自分の中で明確だったからです。根本にある目的が努力する原動力になっていたと思います。
模試の結果、センターの結果、私立大学の受験の結果など、国立大学受験者はそれまでに不安になる要素も、逆に油断してしまう要素も多くあります。しかし、自分の最終目標も最後まで見失わずに勉強し続ける人が最後に合格を勝ち取ると思います。
皆さんも、目標・目的をしっかり持って日々の勉強に励んでいってください。
今まで挙げた方法は基本的で当たり前なものです。
引き続き、他の担任助手が「メンタルの保ち方」について書いていくので、1つのアドバイスと思って参考にしてみてください。
2018年 10月 31日 各科目のセンター対策(理系・上級者向け)
こんにちは、東京大学理科一類一年の野原です。
今回はセンター試験対策について書いていきたいと思います。
皆さんはどのように今までセンター試験で高得点を取るための勉強をしてきたでしょうか。今までの勉強法で結果が出ている、もしくはまだ出ていなくても自分に合っていると思えている方は今から書く勉強法に無理矢理変える必要は全くありません。人によって適している勉強法は異なるのでこのブログが自分にあっている、試してみたいと思った方はぜひ実践してみてください!
センター試験は簡単だと思える人向けではあると思います。あと理系向けです。
心持としては理系科目オール満点を余裕で狙い、英語は9割5分確保で国語、地理(社会科目)を頑張るというのがおすすめです。
ちなみに私は高校三年生になるまではセンター試験のための勉強はやらなくていいと思います。癖が強く二次対策や私大対策の時間が減りその感覚が鈍るからです。センター試験は失敗してはいけませんが多くの受験生にとって本命ではありません。センター試験の勉強をしすぎて二次の学力が志望校のレベルに達さず落ちてしまう確率の方がセンターで失敗して落ちる確率より高いと思います。センター直前で一気に対策していきましょう!
では各科目ごとに私なりの勉強法を書いていきたいと思います。
英語
英語に関しては東進に通っている方はセンター試験本番レベル模試が年に6回もあります。そこでセンター試験の形式には十分慣れると思いますのでセンター試験本番の3週間前まで(2週間前とかでもいいかもしれません)は対策しなくていいと思います。(青字の部分参考)内容としては発音アクセントの確認や一回分まとめて演習をするぐらいです。英語の力がついてくると時間は余ります。
数学
内容はまず二次対策にもなるのですが数学の解法まとめノートを書くことを強くお勧めします。そのノートをつくることで、問題を解き、または解説を読んで瞬間的に把握したその系統の問題にたいしての一般化された解法が言語化され、きちんと自分の頭に定着すると思います。書かないとその分かったという感覚は忘れてしまうのでとてももったいないです。英語同様センター試験本番の3週間前まで(2週間前とかでもいいかもしれません)は対策しなくていいと思います。直前期は東京出版のセンター試験必勝マニュアルという参考書を使いました。センター対策にとても良いと思います。あとは時間が最初は厳しいと思うので演習です。対策すると時間が余ります。
国語
ここが最大の課題です。安定させるのは他の教科と違って非常に難しいです。林先生の「センター対策90%」という講座はおすすめできます。その復習をしっかりとやり、あとはセンター本番の問題で演習を積みましょう。時間がきついです。古文、漢文は勉強すれば安定してくると思います。
物理
二次に向けて勉強していれば2週間ぐらい前からちょっとずつ過去問を解くぐらいで全然大丈夫です。東進生は模試もありますし。
化学
二次のための勉強に加えて主に無機化学のためにセンター用に暗記をすることが大事です。そのために化学もまとめノートを作ってください。何をまとめるかというとセンターの過去問やセンター模試の過去問を解き覚えていなかったところ、あやふやだったところをノートにまとめるのがいいです。全部過去問を解くのは時間が無駄なので問題をみてしっかり選別してください。
地理
私は一カ月くらい前までほとんど何もやらず10日くらいで一気に知識を叩き込み演習を重ねていきました。叩き込む際にもルーズリーフに統計などをまとめました。一気にやるのがオススメです。まとめる際には東進ブックスの「地理をはじめからていねいに」という参考書を使いました。とてもよかったです。
これを参考にして残りわずかなので全力で受験勉強頑張ってください!
2018年 10月 25日 インド留学で得られたこと~夏SHR振りかえり~
こんにちは、東京外国語大学国際社会学部の袴田です。
11月に入り、二次試験の模試などもあり、緊張感も高まっているでしょうか。
私は昨年度、インドに4か月間語学留学をしてきました。
今回は夏に行ったSHRの内容「インド留学BEFORE AFTER」を振り返り、「インド留学で得られたこと」について中心に書きたいと思います。
インド留学を通して得られたこと。
それは、「自分の持つ価値観をより客観的に認識することができた」ということです。
「インドに行くと、価値観が変わる」と言われることがありますが、私の場合、変わるというよりは認識するという言い方の方が近いです。物事を今までとは異なる視点で捉え、自分を見つめ直す4か月間でした。
外国での生活では日本で当たり前だと思っていた日常とは異なります。インドの場合は、水や電気が急に途絶えたり、治安面から夕方以降1人で外に出ることを制限されたり、部屋にネズミが侵入してきたりなど、極端な例ではありますが、日本では想定しないようなことが起こり、毎日が新鮮で新しい発見がありました。そのような状況だからこそ、私は自分の妥協できる限界はどこなのか、人生の楽しさをどこに見出すのか、生活における優先順位など、今まで知り得なかった自分の価値観を知る機会が多くありました。
自分の価値観は生活環境によってだけでなく、多国籍の友人との交流によっても認識しました。日本国内、特に大学内にいる限りは、ある程度はバックグラウンドが似ている人と話すことがほとんどでしたが、留学中はインド人だけでなく欧米や中東の人ともディスカッションする機会が多くありました。彼らとは人種や宗教、育ってきた環境も全く違うからこそ、考え方や価値観、性格も異なります。だからこそ、自分にはなかった考え方を知り、自分の価値観と比較することが出来ました。
このように、今まで経験したことのないことを経験し、出会ったことのない人と出会えることは、留学における良さの1つであり、それによって自分がどんな人間なのかということに気付くことが出来ます。
たった何ヶ月かの留学で性格が180度変わるということはあり得ませんし、私自身の成長も留学だけが理由ではないと思いますが、少なくとも1つの要因であると確信しています。
皆さんの中でも、大学に入ったら留学したいと思う人も多くいるでしょう。
ちなみに私は元々、留学はせずに卒業しようと思っていた人間でしたが、3年生になって現地に行ってインドの言語や文化を学びたい、自分の曖昧な将来の方向性を明確化させたいとの思いから、直前に決めたという次第です。
今から留学したいと思っているのであれば、地道に計画を立てておくことをお勧めします。早くから始めれば、「何のために留学に行くのか」をより具体化することができ、それが奨学金獲得につながることもあります。
留学することで自分の視野が広がることは事実です。留学したい人もそうでない人も、受験生の皆さんは目標に向かって勉強に励んでいってください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
担任助手 袴田
2018年 10月 23日 過去問の解き方~大まかな流れ&分析について~
こんにちは。東京大学1年の海谷です。
本日は過去問の解き方について伝えていきたいと思います。
みなさんは過去問をどのようにして解いていますか。ただの問題集のように解いてないでしょうか。過去問は志望校の合格ラインと自分の現状との違いを把握できる大事なものです。
ここで、私が実践していた過去問の解き方についてお話していこうと思います。
本番と同じ制限時間で解く
↓
その時間内で解けなかった問題を解く
↓
解答を確認して、復習をする
↓
間違えた問題に関して、何で間違えたのか分析をする
↓
分析した事を忘れないようにノートなどにまとめる
この作業を繰り返し行っていました。
ここで意識してほしいのはなぜ問題が解けなかったのかの分析です。
分析をすることで、自分の得意な部分や弱点がはっきりして、何をやれば点数をあげることができるのか明確になります。
分析といってもどういう風に行えばいいかわからない方もいると思うので、自分が行っていた分析を紹介したいと思います。
まず、
知識がなくて解けなかった or 知識があったのに解けなかった
かどうかを判断します。
知識がない場合は覚えれば済むことなので、ここで重要視すべきなのは知識があったのに解けなかったという所です。このことに関して徹底的に分析をします。
例えば、英語で選択肢にnotと書いていたのにそれに気づかずに間違えてしまったとします。その時に、自分の集中力が切れていてできなかったのか、または、思い込みで解いてしまったのかなどを考えます。
バカバカしいかもしれないですが、分析を積み重ねることで、自分の弱点を克服できるようになります。地味な作業ですが、合格へ近づくためには必要なことです。
みなさんが過去問を解くときの参考になれば幸いです。
2018年 10月 21日 自分の過去問演習の使い方~3ステップ~
こんにちは。
早稲田大学法学部三年の鷲野です。
センター試験まで100日をきり、受験生の皆さんは今まで以上に必死に勉強に取り組んでいるでしょう。今回は志望校対策をするうえで欠かせない過去問演習について、私の経験も踏まえて話していきたいと思います。
過去問を有効に活用するために、3つのステップがあります。
①演習
まずは志望校の過去問を解いてみましょう。
演習の時に私が意識的に行っていたのは、
「本番を常に想定して解く」ことです。
私は、試験本番と全く同じ時間割で解いてみたり、周りにも人がいる教室で解いたりしていました。
本番と全く同じような状況を作ることは不可能ですが、工夫して毎回プレッシャーを自ら作り出すこと で、「プレッシャーがかかる状況でも難なく自分の実力を100%出す」という試験本番に必要な力を自然に身につくと思います。
②分析
次に自分がどんな問題を解けなかったか、なぜ解けなかったのかを分析してみましょう。
より高い点数を取るためには、
「解けなかった問題を解けるようにする」しかありません。
そうするためにもなぜ解けなかったのか、その原因を追究して解決していかなければいけません。
私は、間違えた原因を以下のように3つに分類していました。
(1)ケアレスミス
「不正解を選べという問題で正解を選んでしまった」など、よく注意していれば失点を防げたであろうミスをしてしまうことがあると思います。
こういうミスは単なるミスとして軽視してしまうかもしれません。
しかし、何千人という人が集まり一点の差で合否が決まることもある試験本番では、こういった単純なミスが命取りになることがあります。
1、分析をする際にノートを作り、それに自分のミスをすべて書いておく
2、試験問題を解く直前にノートを見て、同じミスをしないように意識してから演習に臨む
こうすることで、大半のミスは防げます。「着実に点の取れる問題を絶対に落とさない」ことも本番においては大きな武器になりえるはずです。
- (2)時間不足
過去問演習を始めたばかりの時期は、試験時間内に解き終われなかったということが多いと思います。
私は演習の際には、科目全体を解き終わるためにかかった時間だけでなく、大問ごとにもかかった時間を軽くメモしていました。
そうすることで、どの問題に時間がかかったのか、なぜ時間がかかったのかというところまで把握することができ、大問ごとにかける時間の目安などの戦略を立て直すことが出来ました。
- (3)学力不足
知識不足など上記⑴⑵以外の不正解の原因がこれにあてはまります。
語彙力不足、知識不足、構文が正しく取れずに意味を間違えた、選択肢で迷って不正解を選んでしまった、などこの中にも色々な原因があると思います。具体的なところまで原因を突き詰めていきましょう。
- ③補強
最後に、分析したことを参考に間違えた原因を解決するための具体的な行動を考えます。いつまでに何をやるかを決め、実際に行動に移していきましょう。
大学入試において満点を取る必要はありません。
分析を踏まえて、上に書いた通り①演習②分析③補強を繰り返しながら
「どの科目でどのくらいの点数を取っていくか」
「その点数を取るために絶対に正解しなければいけない問題はどれか」
を把握し戦略を立てることも同時にしていきましょう。
大変だとは思いますが試験本番において自分を助けてくれるのは、こうした細かく面倒なことの地道な積み重ねです。
ただ単に過去問を解くのではなく、効率良く活用していきましょう!
長くなりましたが読んでいただきありがとうございました。