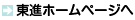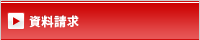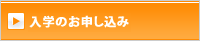ブログ
2019年 7月 14日 [夏]の位置付け
東京大学3年の松澤です。こんにちは。
梅雨真っ只中ですね。連日雨or曇りですっきりしない感じですが、梅雨が明けてしまうとすぐに暑い暑い夏がやってくるのでしょうね。お天気にはいつも振り回されっぱなしです。
さて、タイトルにもありますが、受験生の皆さんはこの夏という期間をどのように捉えていますか?7月3日のブログでは蓮池くんも「夏は受験の天王山」というワードを持ち出していますが、夏の期間は受験においてそれなりに意味ある時期だと私も認識しています。
夏はインプットからアウトプットへの転換点です。
大体7,8月までで授業が一段落します。新宿本科に通う皆さんは、4月から受講を始めた教室一斉授業、映像授業ともに一区切りつく時期なのではないかと思います。
受講修了に伴い、一日の中で自由に使える時間が比較的多くなってくると思います。その時間の中で、今まで使った教材や参考書の内容を整理し直してみてください。特に基礎的な内容に関しては、何も見ずにスラスラ書き下せるようになるまで復習を繰り返してください。いきなり本格的な問題演習に飛びつくのではなく、一旦立ち止まってこれまでの勉強で得たものを再確認するというのが秋からの演習にスムーズに移行するためのポイントです。
また、理系の私からの個人的な意見として、数学の計算練習は夏の間に集中的にやっておくことをオススメします。
私が浪人生の頃実際にやっていた、テキストの問題を5,6個ピックアップし、そのセットを制限時間(80~100分程度)の下で解き切るという、ある種の特訓は非常に効果的でした。計算スピードが速くなっただけでなく、典型問題は絶対に落とさないという自信にもつながりました。
このような訓練を自由にできるのも夏までです。夏は特訓期間とも位置付けることができそうですね。自分に合うやり方でいいので、是非やってみてほしいと思います。
それでは、実りある夏をお過ごしください。松澤でした。
2019年 7月 13日 あとは、実行するのみ。
こんにちは。東京工業大学4年の後岡健太郎です。
今、ダイエットをしているとしましょう。目標はマイナス10キロ。日々、運動や食事制限をして頑張っています。
スタートして1ヶ月が経ちました。1ヶ月でマイナス10キロはさすがに厳しいけど、マイナス3キロくらいはいったんじゃないかな。
そう思ったら、次はなにをするか。体重計に乗って、成果を確認しますよね。
今、カラオケの点数を上げたいとしましょう。目標は90点。日々、歌を聴いたり発声練習をしたりで頑張っています。
スタートして1ヶ月が経ちました。1ヶ月で90点到達はさすがに厳しいけど、開始時点から10点は上がったんじゃないかな。
そう思ったら、次はなにをするか。カラオケで採点して、成果を確認しますよね。
今、大学に合格したいとしましょう。目標は、、、
、、、
そう思ったら、次は何をするか。そうです模試です!!!
模試を受ける目的のひとつとして、自分の現状を知ることが挙げられます。
帳票を見れば、どこが出来てどこが出来ていないのかが明確になります。
そこから自分の現状を分析し、今までの勉強計画のままでいいのか、それとも修正が必要なのか、今後の方向が決まるかと思います。上記2つの例に戻ると
・マイナス4キロ!同じ運動や食事制限を継続しよう!
・5点しか上がらなかった、、、音程は合ってる!けど、リズムがいけないのか。練習方法を再考しよう。
といった感じです。受験勉強だったら
・数学、時間内には解き終わらなかったけど、時間をかけたら解ける問題ばかり。つまり理解はできてるし解けてもいる!課題はスピードだから時間制限を設けた演習を取り入れよう。
・英語、授業でやって1回復習したけど文法問題が全く取れなかった。復習不足かも。毎日1講座ずつ復習、それを長期記憶に落とし込むまでやろう。ただ発音アクセントは安定して得点できているぞ!
といった感じです。
低い成績をとってしまっても、落ち込む必要はないです。自分の現状を素直に受け止めることが、まず大事です。
誉めるとこはきちんと誉めて。ダメなところをどうしたら改善できるか考えましょう。
あとは、実行するのみです。
Just do it!
2019年 7月 12日 夏の模試に向けてアドバイス
こんにちは!担任助手2年の海谷です。
今回はこれから夏にかけて模試が増えてくるので、模試の捉え方について話していこうと思います。
最初に、模試の受け方について話していきたいと思います。
特に東大模試や旧帝大模試などはそうですが、模試の会場には第一志望校を同じとする人たちが多くいます。本番の雰囲気を味わえる良い機会なので、どうせ模試だからと考えて模試の途中で解き終わったから見直しもせずに寝たりするなどのことをするのはもったいないです。緊張感を持って受けることが大事だと思います。
次に、模試を受けた後のことについて話していこうと思います。
模試を受けた後はなるべくすぐに復習をするべきだと思います。模試の結果が出てから復習すれば良いやと考える人もいますが、結果が返ってからだと問問題や試験のときに自分がどう考えてどういう答えを出したのかを忘れてしまうので、復習は早めにやった方がいいと思います。
最後に、模試の結果の捉え方について話していこうと思います。
まず、模試は自分の学力を測るために大切なものですが、模試の判定や結果に一喜一憂し過ぎてしまうこともあると思います。自分自身、模試の結果を気にし過ぎてしまい、勉強に身が入らないこともありました。模試の判定はある程度は大切ですが、それよりも大切なのは自分の弱点や強みを模試を通して明らかにすることだと思います。
模試はあくまでも模試であり本番ではないので、たとえA判定を模試でとったとしても、志望校に必ず合格するという保証ではないので、本番で落ちてしまうこともあると思います。模試の結果を見て、自分に何が現時点で合格基準に足りていないのか、何をすれば本番までにできるようになるのかを考えて、本番までの勉強プランを修正していくことが模試において一番大切なことだと思います。
このブログがお役に立てれば幸いです。
2019年 7月 3日 夏までの勉強スケジュール
こんにちは、東大2年の蓮池です。
「夏は受験の天王山」とよく言われますが、なぜでしょう?
受験には理想的な合格のルートとされるものがあります。夏までに基礎を固めて秋から冬にかけて過去問を演習・研究し実戦力を養い入試にピークをあわせる、というのが王道といったところでしょうか。
現役生は基本的に時間がありません。文化祭や体育祭、日々の学校の授業などに追われてなかなか受験勉強をする時間がとれない。だから夏、時間があるときに頑張って基礎固めを終わらせなければならない。したがって夏で頑張れるかどうか、これが勝敗を分ける…すなわち「天王山」、といったところでしょうか。
浪人生は、現役生に比べて時間に余裕があります。その意味では、浪人生にとって夏は特別な意味を持っているわけではありません。
ただし、浪人生であっても夏までに基礎を固めるというのは同じです。秋以降過去問を演習・研究していく中で「知らない」ことがなるべく少なくなるように今のうちに勉強しておかないといけません。
そこで、浪人生に求められる夏までの過ごし方は、「基礎をこれでもかというくらい詰める」ことだと思います。
焦って色々なものに手を出さない。慢心してレベルの高すぎる問題ばかり解かない。
教科書。授業のテキスト。今までやった参考書。こういったものを何度も復習しましょう。理解が甘い部分があれば徹底的に勉強しましょう。
基礎は決して簡単ではありません。同時に基礎が本当に身についているかを確認するのも簡単ではありません。
入試でいう絶対落とせないレベルの問題。これくらいのレベルが基礎力の確認にちょうど良いと思います。
演習→復習→演習… というリズムで、基礎力に漏れがないか確認していってください。
2019年 7月 2日 模試の結果について
東京大学文科三類一年の佐藤大河です。
今回は模試(特に東大模試や京大模試などのいわゆる冠模試)の結果に対する私なりの捉え方について述べていこうと思います。
まず冠模試は基本的に、その模試の受験者の大半が、その模試が模倣の対象とした大学を受験しうる人によって構成されるはずなので、その模試における志望者内の順位は自らの合格可能性を示す指標として比較的明確なものになると思われます。そういった点で、個人的には、冠模試での順位が高かった時は同じ科類の志望者の大半に優っているという事実が示されたため、自信に繋がりました。そして、その自信があったからこそ本番でうまく立ち回ることができたと言っても過言ではないです。
一方で、模試には判定というものがあります。A判定やB判定、C判定などなど、志望者内の順位よりわかりやすく合格可能性を示しているように思われます。しかし、こういった判定は志望者内の順位という指標に比べて、自分の実力を正確に示すものではないように思えます。そもそもA判定といってもピンキリであって、非常にレベルが高い人もいれば、そこまでレベルが高いわけではない人もいます。さらにA判定でも落ちてしまう人は毎年必ずいるのです。某大手予備校に通っていた知り合いからもらったデータによると、A判定で落ちてしまう人の多くはA判定の中でも低い順位に位置していました。一方でA判定ではなくとも合格する人も当然います。実際に私は1月の東進の東大模試でC判定でしたし、今年理科三類に合格した某氏は同模試でD判定でした。したがって判定というものはあまり気にするべきではないと思います。
以上のことから、模試の結果では判定はあまり気にせず、順位を見ていくことを薦めます。順位が高いことによって自信が高まれば、自信が高まった状態で本番に挑戦でき、自分の解答を信用できるでしょう。本番でビビらないために、順位を可能な限り高めていきましょう。