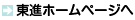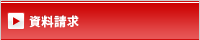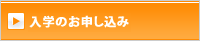ブログ
2019年 8月 2日 状況の変化だけでは、人は変われない
こんにちは。東京大学教育学部3年の青木寧々です。
先日、堀江貴文(通称:ホリエモン)が一冊の本を出版しました。
本の名は『ハッタリの流儀』、表紙には「到底、手に負えないことを『できる』とカマす者だけが最速でチャンスをつかむ!」と書かれています。7/30現在、amazonランキングで4位にランクインする売れ筋の本です。
私はこの本がこんなに売れていることが怖くてたまりません。
本自体を批判するわけではありません。
確かに『できる』とカマせば、自分を必然的に努力せざるを得ない状況に追い込むことはできます。
しかし、大切なのはその後です。
覚悟を決め、努力ができ、結果を出せるか…
それは、全て自分次第です。
状況の変化なんてはあくまで二の次。
状況が変わっても、努力できる人はできるし、できない人はできない。
状況を変えれば自分も変えられるなんて甘い話はありません。
状況が変わったら自分が変わるんじゃない。自分が変わるから状況が変わるんです。
模試で結果が出せない、でも頑張りきれない、つらい、なんで自分が…、と心が折れそうになった時、「あの時は〇〇だったから…」と言い訳したり周囲の状況のせいにしたりするのはむしろ遠回りです。
言葉も、状況も、行動に先行することはありません。行動しなきゃ何も変わらない。
今すぐ行動しましょう。
自戒も込めて、今回はこの辺にしたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
2019年 8月 1日 過去問演習の取り組み方
こんにちは!担任助手2年の海谷です!
もう夏になり日々暑いですね・・
みなさん体調は大丈夫でしょうか。体調管理も受験生にとって大事なことなので、しっかり水分をとって、寝るときはきちんと寝て夏を乗り切りましょう!
さて、今回は夏になり過去問演習を少しずつ行い始める人もいると思うので、過去問の取り組み方について述べていこうと思います!
まず、過去問を解くときのことについて話していこうと思います!
過去問を問題集みたいに解いていないでしょうか。過去問は問題数が限られているので、それではもったいないです。
少なくとも過去問を解くときは、時間制限を設けて緊張感をもって解きましょう!
そして、過去問を解いた後、復習について話していこうと思います!
解いてその後採点してそのまま終わりという人はいないでしょうか。
一番過去問を解く上で大事なのは、この復習・分析です。
過去問を解いて復習するときに、なぜこの問題ができなかったのか・なぜ時間が足りなくなったのかを分析するようにしましょう!そうすることで、自分に何が足りていないのか、何を勉強すればいいか分かります。
また、ああ単なるケアレスミスだったではなく、なぜケアレスミスが起きたのか(例えば、字が汚かったなど)まで考えるようにすると次に過去問を解くときにどういう行動をすればいいか分かります。
過去問を最大限有効活用するために、復習・分析をしっかり行いましょう!
このブログが少しでもみなさんのお役に立てば幸いです。
2019年 7月 31日 大学生になって感じる、勉強で大切なこと
こんにちは、担任助手の蓮池です。だいぶ暑くなってきましたね。体調管理に気を付けていってください。
東京大学では2年のこの時期に専門とする学部を決める所謂「進振り」があって、実は今ちょうどそのシーズンです!ですから今は皆点数と学部の話でもちきりです。「進振り」では皆が皆行きたい学部に行けるわけではなくて、人気のある学部はそのぶん高い成績を要求されます。
皆さんに驚愕の事実をお伝えしましょう。それは東大ではよく「入試の成績と大学での成績には相関がない」と言われていることです!確かに入試で抜群の成績だったのに大学での成績が良くない人、入試ではあまり良い成績ではなかったけど大学に入ってから良い成績の人、色々です。
そこで、今日は大学生になってひしひしと感じる「勉強で大切なこと」について書いてみようと思います(笑)。
ズバリ言うと、やはり勉強で大切なのは「継続力」と「集中力」だと思います。
受験生の皆さん、学校とかでたまにいる「勉強してないけど賢い人」に憧れていませんか?
「地頭」とか「才能」という言葉に踊らされてはいけません。
大学の授業である教授がおっしゃっていたことがあります。そんなの「誤差」みたいなものだ、と。
確かに記憶力にも集中力にも個人差はあります。得意なことも苦手なことも違うでしょう。
しかし、皆人間です。たぶんゴリラから見たら皆一緒です(笑)。
「地頭」なんてそんなたいそうなものじゃないんです。大学以降、やはり成績が良い人は凄く勉強しています。コツコツ勉強しています。そうでなきゃ太刀打ちできない。学問は「地頭」のみでなんとかなるほど浅くはないですよ。先の先までいけば「才能」も問題にはなるでしょうが…
コツコツ勉強する。やると決めたら集中して勉強する。この癖を受験生時代につけておきましょう。
以上になります。ありがとうございました。
2019年 7月 30日 印象的だった講義について語る
東京大学文科三類一年の佐藤大河です。
そろそろ私の大学では期末試験が終わる頃です。そこで今学期を振り返った際に印象的だった授業であるALESAについて紹介させていただきたいと思います。
このALESAというのはActive Learning of English for Students of the Artsの略で、東大の文科生向けに開講されている、英語で短めの論文を書こうという講義です。最終的な語数は大体1500語くらいですが、クラスや人によっては、2500語ほど書くことを要求される場合もあったようです()
授業は15人程度の少人数制で行われ、そのメンバーは基本的に同じクラスの人で構成されるようです。また、担当教員によって授業の進度や課題の多さ、生徒に要求するレベルはかなり異なっていて、私の場合だと一週目は課題が重く感じられたものの、終盤にはその感覚が徐々になくなっていったように思われます。その一方で、別の担当教員の講義を受けていた人で、一週目の課題は少なかったものの急激に課題の量が増加し、今週の火曜日か水曜日くらいまで最終課題に追われていた人もいたようです。
教員に対しては基本的に英語しか使えませんが、授業内の生徒間での会話においては日本語を使って話すことの方が多かったように思われます。
講義の終盤になると、プレゼンが始まります。このプレゼンは自分が設定したテーマを発表しようというもので、もちろん英語で行います。そしてプレゼン後には、軽くディスカッションをすることになっていて、これも英語で行われます。
講義では剽窃を防ぐ方法も学べます。剽窃とは、他人の考えや文章を無許可で使用し、自分のものとしてしまうことです。ダメですよね。
次にテーマの研究方法について述べますが、私の場合は教員と面談して、救済措置としてとある雑誌(Foreign Affairs)を提案されたので、それを用いて調べていきました。普通はTreeやGoogle Scholarなどのサイトを用いて調べていくようです。
これを機会として御自身が志望する大学の授業を調べてみてはいかがでしょうか?モチベ向上につながるかもしれません。
2019年 7月 15日 夏から本格的なアウトプットへ
こんにちは!早稲田大学1年の志波です!
そろそろ夏休みになりますね!!
よく8月は受験の天王山と言われるようにとても重要な1ヵ月です!
そこで今回は夏休みに必ずやっておくべき学習方法を紹介したいと思います!
その方法というのはインプット→アウトプットの流れで基礎の復習を徹底することです!
まず初めにやることは、
英語であれば英単語・英熟語・英文法・英文解釈
古文であれば古文単語・古典文法・古文常識・和歌の修辞
といったようにその科目を要素ごとに分けて、それぞれの分野で定着していない知識などが無いか細かく見ていき、あれば再びインプットしていきます。
この一連の流れで8割方インプット出来たら今度はアウトプットの作業に移っていきます。
アウトプットの具体的なやり方としてはとにかく色々な問題を解いて演習をし、そこで発見した弱点を再びインプットしていきます。
なぜアウトプットの作業が必要なのか? インプットが100%できればそれで完璧になるでしょ?
と疑問を抱く人は多いと思います。
しかし、インプットで全ての穴を埋めることは実際不可能です。
主な理由として、同じ答えを問う問題があったとしても問題の切り口が違ったり、与えられるヒントに差があるなどインプットしたままの形式で試験に出ることが多くは無いからです。
だからこそアウトプットする必要性があるのです。
試験本番ではどんな問題が出るか分かりません。
本番でどんな聞かれ方をしても即座に答えられるようにこの夏で色々な問題に取り組み、多角的に知識を使えるようになってほしいと思います!!!