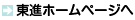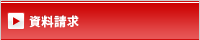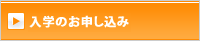ブログ
2019年 8月 11日 意志の弱い人ほど工夫が必要
こんにちは!担任助手1年の水口絢です。
みなさんは最近家と塾の往復の日々で日光を浴びる事が少ないと思いますが、健康の為にもリフレッシュの為にも少しは日にあたる事をオススメします!今回は東進の登校時間(8時半〜19時)以外での私の勉強について書きたいと思います。
まず、朝は8時半に毎日登校していました。ですが、通学に1時間弱かかっていたので、そこでは必ず勉強するようにしていました。私は意思が弱かったので、現役の時は電車では携帯を見てしまいがちでした。それを改善しようと思い、浪人生の時は家を出る前に勉強道具を手に持ち、携帯はポケットではなく鞄の中に入れていました。電車に乗った時に携帯を1番いじりづらく、勉強を1番しやすくしていました。また、勉強の内容も単語帳などただ眺めるような飽きてしまいがちなものではなく、数学の問題を実際にペンを動かして書いてたりしました。(周りの人にびっくりされることは結構ありました笑、あとおばあちゃんにいきなり応援されることも笑)満員電車すぎてそれが出来ない時は、英語の長文の問題集(選択肢)をやってました。
次に、夜は、家では勉強を全くせず、東進に残っていました。ですが、帰る時間を毎日決めていたのではなく、その日その日やる事を決め、それを終えたら帰っていました。なので19時に帰る時もあれば、閉館まで残っていた事もありました。時間で区切ると、例えば20時まで勉強することが目標になってしまい、学習自体に集中出来ないと思ったからです。ここで気を付けていた事があって、ここでもう終わりにしようと思ってから、一つだけ勉強をして帰るようにしてました。(5.10分くらいでできること、その日に見た映像の復習を軽くとか)
私の時間の使い方はこんな感じです。ここで紹介する事で、皆さんの助けに少しでもなれば嬉しいです。私も浪人時代毎日これが出来ていた訳ではありません、1ヶ月に一度とか休息の日を決めてました。まだまだ先は長いので、自分が継続しやすい方法で頑張って下さい、応援しています!
2019年 8月 10日 楽しんで爆進する方法
こんにちは。東京工業大学4年の後岡健太郎です。
早いもので、もう8月。8月と言えば、受験の天王山なんて言ったりもします。
今現在、第一志望に向けて爆進中!という方は、引き続き、さらに爆進してください。
一方、爆進したいけどやる気がでないよ、、、という方、この記事必見です。
そもそもなぜやる気がでないのか。それは勉強=苦行という認識があるからかもしれません。もちろん、この認識で、「この逆境に打ち勝つ!!」という反骨精神が持てる人はそのままでいいと思います。ただやはり、苦しいものは苦しいですよね。
ではここで、やる気が出るときはどんな時か、考えてみましょう。
私は小学生の時、最高の集中力でテレビゲームをしていました。1日30分というルールなんて知ったことか、あっという間に3時間。めきめき上達しました。
一方、半ば強制的に通わされたスイミングスクールでは、なんて時間の経過が遅いこと。集中力の欠片もなく、泳力もあまり変わりませんでした。
この2つの違い、それは集中してるかどうか、もっと言えば楽しんでいるかどうかです。
ではどうやって楽しむか。それは成長を実感し、相応の結果を得ることだと思います。
ゲームの例では、敵を倒すことでキャラクターがレベルアップし、ボスを倒せるようになる。
一方スイミングでは、まずレベルアップを想定していないため能力が変わらず、昇級試験にも合格できない。
勉強でも、これをしたら学力が上がる!という認識を持つと持たないのでは、得られる結果が変わってくると思います。
まずは授業を受け、それをアウトプットし自身のレベル上げ。そしてテスト(どんなに小規模なものでもいいです)や復習でレベルが上がったこと、つまり成長を実感してください。これができてくると勉強が楽しく感じ、集中もできると思います。
他にもゲームのように、友達と競ったり、目標を達成したら自分にご褒美など、楽しめる手段は色々あると思います。
受験という贅沢な機会。だらだらと進むのではなく、せっかくなので爆進して、楽しんでみてはどうでしょうか。ラスボス倒すと、最高に気持ちいいですよ。
2019年 8月 9日 目的を持って復習しましょう
こんにちは!早稲田大学法学部2年の下崎です。毎日暑い日が続きますね。しっかり水分補給して、熱中症にならないように気を付けましょう!
さて、今回は担当生徒から質問もあったので私の浪人生時代の各科目の復習の仕方について書いていきたいと思います。
まずは英語。この時期は長文の受講がメインでした。最初は板書を写したノート等は見ずに、受講した後すぐに授業を思い出しながら、自分がどの点に気を付ければ正解できたのかを考えます。それでも曖昧なところはノート等で確認していました。正しい解答プロセスを定着させることを1番に意識していました。単語や熟語などは、毎日欠かさずやりました。具体的には、高速基礎マスターの1800~上級英熟語までと、システム英単語、英検準1級のものをやっていました。市販の単語帳は自分に合ったものが良いと思いますが、高速基礎マスターは絶対に繰り返しやった方が良いと思います。一度完全修得したらやらないという人や、もうほとんど覚えているからやらないという方も多いですが、誰でも簡単なものを急に忘れてしまうということはあると思います。それが模試や入試本番であったら勿体ないです。簡単な単語や熟語を常に素早くアウトプットできるようにしておくことは大切だと思います。
次に国語。現代文は英語の長文と同じく、どこが問題を解く上で重要なポイントなのかをもう一度考えながら、読み直していました。そして何度も何度も同じテキストを繰り返し復習していました。確かに答えは覚えてしまいますが、重要なのは解答プロセスの定着なので、解き方を確認した後は初見の問題を解いてみるなどしてアウトプットしていました。古典に関しては、苦手だったのでまずは基礎基本を身に付けることを第一に考えました。ライブ授業の先生から頂いたプリントをひたすら見返していました。夏は他の科目に比べて、国語に少し多く時間を割くように心掛けました。そのおかげもあり、8月以降の模試の点数もあがりました。比較的時間のある夏に苦手科目を克服すると良いのではないかと思います。
最後に世界史です。世界史は問題集や模試で間違えたところは、まず解説を見ずに教科書やテキスト・資料集を使って自分で調べて解答を導くようにしていました。そしてさらに用語集で調べ、ノートにその説明を写していました。試験や模試の前などは、そのノートを見返し自分が間違えやすい点を確認していました。
ただ、復習するのではなくそれぞれ目的をもって復習することが大切だと思います。
辛いこともあるかもしれませんが、これからも本番まで頑張ってください!
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
2019年 8月 8日 勉強しないと、社会に出るのが4年遅れます
こんにちは、担任助手1年の稲田です!
大学は夏休みに入り、これからオープンキャンパスに行く人も多いのではないでしょうか。
オープンキャンパスに行って、良い大学だな、通いたいと思ったり、この大学は嫌だなと思ったりすることと思います。
さて、今回のブログで、僕が伝えたいことは何かしっかりとした目的をもって大学に入学して頂きたい、そして大学に入ってからもしっかりとその目的を遂行してほしいということです。
以前、大学の構内で
バイトとサークルで忙しくて全然勉強できてない~
という声を聞いたことがあります。
もちろん、バイトすること、サークルに入ることが悪いと言いたいわけではありません。
むしろ大学生のうちに経験しておいた方が良いものだと思っています。
しかし、バイトもサークルも大学生の本分ではありません。
それらが原因で勉強しないまま卒業するのでは、ただ社会にでるのが4年遅れてしまうだけなのではないでしょうか。
大学の授業だけではなく、資格の為の勉強や、留学するための外国語の勉強など将来のためになる勉強をしっかりとしたうえで、卒業をすることで、4年間の大学生活は意味のあるものになるのだと、僕は思います。
そうした意味のある大学生活をおくるためにも、まずはやはりしっかりとした目的をもって大学に入学することが大切です。
入学してから様々な事に出会い、その目的が変わっても良い。ひとまず、現状を顧み、将来のことを考え、自分と向き合うことで現時点での目的をしっかりと定めてもらいたいと思っています。
まだまだ猛暑は続きますが、冷房や扇風機をつけ、水分をしっかり取るなどして、体調を崩さないように気を付けていきましょう!
2019年 8月 3日 大学の勉強
こんにちは。東京大学の松澤です。
ちょうど昨日大学で試験が終わったので、大学での授業や試験がどんなものか説明してみたいと思います。
講義にはさまざまな形式がありますが一番多いのは、広い教室で教授1人が数十、数百人の学生相手にずっとしゃべり続けるタイプだと思います。講義中教授と学生とのコミュニケーションはほとんど無く、講義終了後に数名の学生が直接質問しに行くぐらいです。この手の講義は、興味が無ければ退屈に感じることもあるかと思います。講義に出るのをサボる学生もちらほらいます。
講義の他には、演習、実習、実験、ゼミなどの授業もあります。
試験は成績評価方法の1つで、試験の他にレポート課題や出席回数などで評価をつける場合もあります。その講義を担当する先生が作るので、難易度や形式は先生によってバラバラです。単位を取るには一定以上の成績を修める必要があります。
大学で学ぶ学問は非常に難解です。私は数学の授業をいくつか取っていますが、話が抽象的すぎたり、式変形が高度すぎて本当に何を言っているのか分かりません。講義を聞くだけ、板書を写すだけの受け身の勉強では、残念ながらほとんど実力はつかないのです。(それでも単位は取れてしまいますが)
大事なのは、講義で習ったことを反芻し、自分が理解できる形に落とし込むことです。
ノートを見返したり、本や文献を読み漁ったり、演習問題を解いてみたり、友だちと教え合ったりすることで、初めて力が付き始めます。
…というのが大学生のあるべき姿なのですが、サークルなり、アルバイトなりをやっていると学業をおろそかにしてしまうこともしばしばあります。恥ずかしながら私もその一人です。
少なくとも自分が興味のある分野、専門としたい分野については本気で学ばなければなりません。そうでなきゃ、大学に行く意味がありません。
大学での勉強はそんな感じです。やりたいことができるというのは事実なので、そこに関しては期待して良いと思います。
以上、松澤でした。