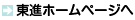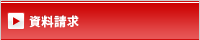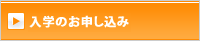ブログ
2019年 9月 12日 (私大向け)夏以後の日本史学習について 前篇
お久しぶりです!慶應経済3年の長谷川です。
学習進捗の方はいかがでしょうか。そろそろ基礎となる内容の受講と復習を一通り終えて、過去問演習に入る方も出てきている頃かと思います。学習内容がかなり変わってくる時期だと思いますので、しっかりと各教科でゴールを明確にし、逆算して計画を立てましょう。
今日は少し該当者がしぼられてしまうのですが、学習内容の変わり目ということで、今後の日本史の学習の指針を示せればと思います。
日本史に関しては、学習方法は違えど大まかにやるべきことは皆同じです。
①通史の定着(反復)
②文化史
③演習(+志望校対策)
この3つです。ちなみにこの時期なので通史の受講は終えていることが前提です。1つずつ見ていきます。
①通史の定着(反復)
まず間違いなくこれが一番大事です。ここで言う「定着」のレベルは、教科書内の内容で聞かれたことは90%以上答えられる、を目安に考えてください。もちろん100%を目指したいところですが、あの膨大な範囲と語句量を完璧にすることを目指すと切りがありません。覚えられていないものは直前期にピックアップすれば問題ないので、今は完璧でなくても全体を頭に入れることを目指しましょう。
具体的な内容としては
・教科書orテキスト
・ノート(大まかな流れを確認できるもの)
・一問一答(アウトプット用教材)
の三点で十分だと思います。早い段階から資料集や用語集を使っている人もいますが、大事なのは得点効率に合った学習をすることです。先述の三点から8割以上が出題されるにもかかわらず、そこが定着していない段階で残りの2割以下に力を入れるのは非効率ですよね。上記三点だけでも全体を定着させるのはかなり難しいです。まずはここを押さえましょう。
一問一答については使っていない人もいると思います。あくまで教科書やテキストで頭に入れたものをアウトプットするためのものなので、それに代わるものがあれば構いません。ただし一般的な問題集よりも、用語量、試験範囲のカバー率やアウトプットの効率などで勝るので、早慶上智の受験者は特別理由が無ければ一問一答の利用をおすすめします。
これらの具体的な学習サイクルについては人それぞれに合ったやり方があるので、今のやり方で上手くいっていない、定着度がなかなか上がらないという人は、是非校舎にいる各担任助手にそれぞれの学習法を聞いてみてくださいね。参考になることも多いと思いますよ!
長くなってしまったので、今回はここまでにしたいと思います。読んでくださったみなさん、ありがとうございました。
次回は②の文化史と③の演習と志望校対策をメインに書いていければと思います。
それでは後編で!
2019年 8月 22日 夏以降の勉強
こんにちは、千葉大学医学部2年の海邉拓実です。今回のブログでは夏以降の勉強について書こうと思います。
まず現役生、特に高校2年生、高校3年生にとっては夏はいわば受験に向けてのスパート期であったと僕は考えています。というのも、高校2年生は夏期講習などをきっかけに受験を意識し始め、高校3年生は学校がない時に自分で毎日勉強をして基礎力を固めます。そして夏以降の勉強に備えます。
一方浪人生はどうでしょうか。確かに浪人生は現役生と同じようにきちんと勉強をするのですが、正直夏以前と勉強量や内容などに大きな差はありません。正直中だるみしてしまう人が出てきてしまうのは確かです。
現役生が受験に受かるのはこの夏にきちんと固めた基礎力が夏以降の勉強にしっかりと活きてくるからこそ応用問題等の演習で力が付き、どんどん成績があがるからだと僕は考えています。
逆に浪人生が2度目の受験にも関わらず残念ながら入試に合格できない理由は、夏の中だるみによって基礎力が固められずその後の演習の効果が薄れてしまっているからではないでしょうか。
いよいよ、この夏が終わろうとしています。
ここまできちんと勉強できてきた人、是非このまま勉強を続けて下さい。きっときちんと固めた基礎力が今後の応用演習に活きてくると思います!
あまり勉強できなかった人、確かに夏は取り返すことができません。だからこそ、これからの自分の勉強計画を今一度見つめ直しましょう。本当にこのまま演習に進んでしまっていいのでしょうか。基礎力は十分でしょうか。効果があまりない演習をするよりはきちんと基礎力を固める方が大切だと僕は思います。これからの努力次第で十分巻き返しは可能です!
是非皆さんこれからも頑張りましょう!!
2019年 8月 21日 学習の優先順位
こんにちは。東京農工大学4年の大下です。
8月に入り、気温から見ても本格的な夏になりましたね。室内で勉強しているとはいえ、昼休みの外出等で熱中症になる可能性もあるので注意してください。
今日は「学習の優先順位」についてお話しようと思います。
皆さんそれぞれで取り組んでいる教科、講座や問題集があると思いますが、それらに優先順位はつけていますか?
「今、やれることをがむしゃらにやっている」、「成績が伸びそうなことを中心に学習している」、「今は○○の講座が沢山余っているのでそれらを優先して取り組んでいる」といった方針で学習を進めている人はもう一度「学習の優先順位」を見直してみたほうがいいかもしれません。
今回のブログで伝えたいことは、学習の優先順位は長期的な計画から逆算してほしいということです。
直前の模試や残っている講座数を意識することも大切ですが、それ以上に2月末の合格を意識した優先順位付けをしましょう。
例えば、センター及び私大・二次試験でも大きな割合を占める英語・国語・数学の優先順位は上位に来るはずなので「これらの主要科目を全く学習しない日を作る」という計画は長期的な優先順位付けを意識できていないと感じます。
或いは「数学は伸びそうにないけど、理科科目は伸びそうだからそちらに割り切って学習を進める」ということも、”効率的に成績を伸ばす”ことに意識が向かってしまい、最終的な合格を意識した学習とは言えません。
「自分は大丈夫!」と思っていても、毎日学習を進めるうちに段々と優先順位を見失っていくことはあるかもしれません。定期的に合格を見据えた数か月単位の予定を立て、”本当に必要な学習は何か?”を常に考えるようにしましょう!
担任助手も全力でサポートします!
今日のブログはここまでです。ありがとうございました。
2019年 8月 20日 深く理解する
どうも、そろそろ夏も終盤、帰郷していろいろなことを懐かしむ担任助手1年の天羽淳椰です。今日は僕が勉強をしていく中で一番大事にしていることを紹介したいと思います。それは、深く理解するということです。
たとえば、数学の勉強をするとします。数学の勉強はいわゆる公式というものを理解した後に演習をすると思います。皆さんはその公式をどの程度理解しているでしょうか。数学の公式はとても便利で一回覚えてしまえばあまり考えずに使え、時間短縮にもなります。
しかし、公式には大きな落とし穴があります。それは、理解をしなくてもある程度問題が解けてしまうことです。確かに、公式を覚えるだけで大学受験に出てくるすべての問題が解ければいいのですが、大学受験の問題はそう簡単にできてはいません。公式を覚えるだけで問題が解けるならみんなできてしまって差がつきません。
さらに、もう一つの大きな落とし穴は、公式を使うことに甘んじて、理解したことを忘れることです。一回、その公式について理解したことも使わなければ忘れます。公式自体は楽に使え、頻繁に使っているので忘れません。しかし、最初その公式について理解したことを忘れ、公式ありきで問題に取り組んでしまいます。これでは、公式という名ばかりの付け焼刃です。
皆さんが陥りやすい例を紹介したいと思います。微積の面積公式です。皆さん、高校の教科書で一回は見て、そして高校の先生に、「面積の公式は〇個あるから、覚えなさい。」と言われ、むやみやたらと覚えた人もいると思います。しかしその公式が使えるのは一部で、それ以外は、がむしゃらに計算する、って思っていませんか。公式の理解が浅いと、無駄な計算に走り、計算間違いをしやすくなります。面積の計算はほとんどいわゆる公式と呼ばれるもので処理できます。しかし、それが実現できたのはその公式を真に理解したからです。
公式の理解を怠らずに真に理解するとその公式の効果は絶大になります。また、理解したことを忘れないように復習すると本質的な数学の勉強ができ、自分の数学力が上がっていきます。皆さんも公式を深く理解して数学力を上げていきましょう。
2019年 8月 12日 結果を出すか出さないか、その分水嶺
こんにちは。東京大学教育学部3年の小川です。
突然ですが、みなさんに質問です。
受験に限らず、またどんなに小さいことでも良いです、これまでに何かしら工夫をしてみて、そしてそれが成功した経験はありますか?
ほとんどの人が、何かしら1つくらいはあるんじゃ無いでしょうか。
ちょっとしたことで良いんです、人前で話し始めるときに沈黙を作ってみる、とか。
その上で、さらに問いかけます。
その上手くいった工夫を、あなたは今も継続していますか?
リーダーシップ論の専門家であるジョン・マクスウェル氏は、結果を出すか、出さないか、その分岐点として、この「成功事例の継続」の有無を挙げています。
結果を出す人間は、結果を出せない人間がたまにしかやらない良い行いを、息をするようにやり続けている。それゆえに結果を出し続けられている。
と彼は言います。
もちろん、これが結果を出すための必要十分条件であるというつもりはありません。ただ、重要な必要条件の1つではあるでしょう。
さて、改めて、一度これまでの浪人生活を振り返ってみてください。
どうでしょうか、一回上手くいったきりで満足してしまい、その工夫を継続せずにいることはありませんか?
もしあるのなら、すぐにまた再開しろとは言いませんが、確認して欲しいことが2点あります。
・なぜそれを継続できなかったのか、いかにして今後は継続できるのか
・今また再開するとして、さらに何かブラッシュアップはできないか、もしくは他の分野への応用はできないか
上の2点を確認し、その上でまた今後の学習や演習にうまく組み込み続けてほしいなと思います。
スポーツの世界において、スランプに陥ったときには、結果が出ていた調子のいい時期の自分自身のフォームを確認し、現在のズレを修正しようと試みることがあります。
みなさんも、時として過去を省みる時間を設け、過去の自分から学び取ることを忘れないでください。
少しでもこの記事が参考になれば幸いです。
小川