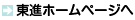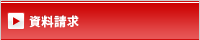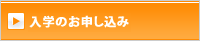ブログ
2021年 7月 13日 この夏、ちょっとだけ攻めてみませんか
こんにちは。担任助手2年の大類です。
気付けばもう夏ですね。移ろう季節の中、どんな思いを抱えながら机に向かっているでしょうか。
果たしてこの夏をどう生かそう・・・ここで一気に差をつけたい、苦手科目の克服に重点を置きたい、4月からの遅れを巻き返さなければ・・・それぞれ思うところがあると思います。「浪人生の夏は6回やってくる」といえど、やはり受験生にとって夏は特別な時期であることに変わりはないようです。
さて、受験勉強には大きく分けて2つのタイプがあるように思います。一つは、基礎知識や典型解法の暗記・修得に始まり、実際に試験の現場で運用できるようにするという「点を落とさない」ための勉強、もう一つは、初見問題や難問が出題された際にも焦らず対応し、点数に繋がる答案を書けるようにするという「点を獲る」勉強です。今回は前者を「守りの勉強」、後者を「攻めの勉強」と呼んで区別することにしましょう。
4月から皆さんが行ってきた勉強は、この「守りの勉強」の土台固めだったと思います。もちろんこの勉強は、受講のテキストや単語帳・一問一答の反復という形で最後まで続けていかなければなりませんし、演習の過程で更に磨き上げていく必要があります。しかし、難関校になればなるほど、この守りの勉強だけでは足りず、攻めの勉強も行わないと他の受験生との差がつきにくいという現状もあります。
そこで、一つ提案をしたいと思います。この夏、少しだけでも「攻めて」みませんか。
タイムリミットが刻一刻と迫る中、浪人といういわば後ろ盾のない状況で、ついつい守りに走ってしまいがちなのはよく分かります。しかし、守りを固めるだけでは本番は乗り切れません(そもそも、受験本番までに完璧に守りを固められる人はほぼ皆無であり、皆何かしらの不安要素を抱えて試験に臨むことになります)。
余裕がないように見えて実はまだたくさん余裕があるこの夏の間に、一日数分でも良いので、合格者正答率の低い問題や典型から外れた難しい問題に果敢に挑むなど、ここで「攻め」を一度経験しておけば、秋から直前期にかけて本当に後がなくなった際、他の受験生が守りに入る中、心理的な余裕を持って「点数を獲る」勉強をのびのびと続けることができるはずです。
体調にはくれぐれも気をつけて、各自勉強を続けてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2021年 7月 12日 5秒で始める勉強
こんにちは、担任助手1年の瀧本です!
7月のこの時期までは、まだまだ授業や基礎事項の確認等、あなたに課せられた”やるべきこと”がペースメーカーとして上手く機能し、順調に学習が進められているという人は多いのではないでしょうか。
その一方で、そろそろ始まる夏休み期間は、勉強における自由が手に入ることと引き換えにあなた自身が一日一日勉強する内容を決めて、それをきちんとしたペースで継続させていく必要がある期間です。
自分でペースを決めなければいけない、そんな期間だからこそ大敵となるのは、先延ばしの習慣です!今回は、そんな先延ばしの悪習慣は断ち切ろう!というテーマです。
先延ばしは、何かしらの行動の切り替え時に起こります。数学の大問5が終わって、6は明日にしようという人はいても、5を解いている最中に途中で解くのをわざわざ止めてそれを明日に回そうとする人はいないと思います。これはどうやら人間の脳が恒常性を維持する行動を好むから、らしいです。
そんな先延ばしを止める効果的な方法を紹介している人がいます。
思ってから5秒以内にその行動を始めることです!
その人が言うことには、人間は新しい行動を始める際に、5秒の時間で、行動を止めさせるように脳内で適当な論理を組み立てることができるそうです。
つまり5秒以内に行動を開始すれば、先延ばしせずに済むというものです。
二度寝をする人は、目覚めてから5秒以内に起きれば、あと10分なら大丈夫だと思うこともなく起きられるということです。
実践するのは難しいと思いますが、効果的ではあると思います。
自分で立てた計画はしっかり管理できても、その時々の感情を管理することまでは難しいです。
ただ、勉強は①自分にとって正しい計画を立てること、②計画を継続して実行できることの二段階の関門をクリアして上手く進めていけるものだと思います。
勉強の時間のはずなのにこれを見ている人、5秒以内にブラウザを閉じましょう。
勉強頑張ってください!
2021年 7月 10日 夏前に確認してほしいこと
こんにちは!担任助手1年の志波響香です。
本科生として勉強を始めてから3か月、勉強の調子はどうでしょうか?
7月に入りだんだん暑くなってきたので、体調を崩さないように気を付けていきましょう。
さて、今回は夏前に確認してほしいことについて書きたいと思います。
本科生は高校生と違い、行事などの節目となるものが少ないので、ぼんやり勉強してしまうように思います。メリハリをつけて勉強していくために、これから書くことが少しでも役立てば嬉しいです。
1. これまでの学習についての振り返り
4月からの勉強していく中で、出来るようになったことや未だに苦手なことがあると思います。そこで夏に入る前に、なぜできるようになったのか、またなぜ未だに苦手なのかを考えてみましょう。例えば、英語の点数が伸びたという生徒であれば、「高速マスターを毎日やり続けたから伸びた」、「修了した受講の復習を反復していたから伸びた」など様々な要因が考えられます。このように自分の学習の振り返りをすることで、「~をしたから点数が伸びた」ということがわかり、点数につながりやすい学習ができるため、効率良く学習を進めていくことができます。
もし直接的な原因がわからない場合は、自分の学習の仕方を振り返ることでもいいと思います。例えば、得意科目ばかりに時間をかけてしまっていたり、復習に時間が割けなかったり、反省点があれば、夏に入るこのタイミングで改善できるようにしていきましょう。逆に、成長した、上手くいった点を振り返って、夏からまた実践していくことも必要です。
2. 苦手分野に取り組む
受験科目を均等に学習していくことも大切ですが、苦手を残したままでいると、受験では不利になってしまうことも多いです。特に私立の人は3科目受験なので、気を付けましょう。しかし、苦手分野はやっていても解けないし、面白くないといって、後回しにしてしまうことが多いと思います。私も実際現役の時、国語が苦手で後回しにした結果、滑り止めとしていた学校でさえ不合格になりました。夏の間に苦手を克服するのは難しいと思いますが、せめて毎日取り組むなどして、苦手意識をなくしていってほしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2021年 7月 9日 勉強の質を上げるための効果的な習慣
こんにちは。担任助手の佐々木です。7月になり気温が暑くなりましたが、体調は大丈夫ですか?
さて今日は勉強の質を上げるために身につけてほしい習慣について話したいと思います。
勉強の質を上げる習慣とは、一つ一つの勉強に目的を持つことです。目的を持つことによって、具体的な目標を決めやすくなったり、するべきことが明確になります。
「〇〇大学に受かりたいから、模試でこの点数を取る必要があり、そのためにこのくらい勉強する必要がある」という思考がわかりやすいです。このように大まかな目的・目標を設定している人は多いです。しかしみんなと差をつけたいならこの目的をより細分化し、設定する習慣をつけるのが効果的だと思います。
みなさんは新たな講座や参考書など始める時、それらを一通り終了した後のことを考えていますか?「授業をうけたり、参考書・単語帳に取り組めば点数が上がるだろう」と漠然と考えていませんか?授業を始める際に、最初に目的を考え、それを意識しながら受講に取り組む人とそうでない人とでは受講を完了した際に大きな差が生まれています。
例えば、長文読解の授業を始める時に「早慶英語の長文読解をするためにこの授業を受ける」という目的を設定したとしましょう。それにより、早慶の過去問を始める時期より前に終わらせるという具体的な目標が出来ます。さらに授業前に一度早慶の過去問を解き、自分がつまづくところを把握して授業に臨めば、先回りして苦手克服ができるかもしれません。それだけではなく早慶の問題の分量や時間配分なども想定して予習ができたり、復習の際にどのくらいのレベルの単語まで覚える必要があるのか分かります。もし目的を持っていなければ難しいからと見逃してしまう単語や文法を目的を、到達するべきレベルが分かってればその時に覚えようと意識することができます。
このように最初に一つの勉強に目的を持つことで、勉強に取り組む意識を大きく変えることができます。一気に意識を変えることは難しいと思うので、「一つ一つの勉強に目的をもつ」という方法を試してみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
2021年 7月 8日 復習について
こんにちは!担任助手3年の稲田です!
だんだんと外は暑くなってきて、夏がはじまったなという感じがしますね。
これくらいの時期から、あるいは、もう少ししたら、過去問などの演習を始める人が多いのではないでしょうか
ということで、今回は、演習の復習についてお話したいと思います。
皆さんは、演習の復習をどのように行っていますか?
間違えた問題だけ解き直したり、ただもう一度通して解いたりするだけになっていませんか?
実際、自分も高校生の頃に、そのような復習の方法を行っていた時期もありました。しかし、その方法で成績はあまり伸びませんでしたし、効果的ではないと今は思っています。
間違えてしまった問題に対しては、解けなかった理由を考え、解答、解説、参考書等で確認し、自信をもって解答できるようにする。
これは復習をするのではあれば、ほとんどの人ができていることだと思います
では、正解した問題についてはどうでしょうか?
単語や文法などにある、ただ知っているか知らないかを問われているような問題は別として、根拠をもって解答する必要がある問題を、なんとなくで当ててしまった時、その問題の復習をきちんと行えていますか?
例えば、記述式で言えば、どうしてその解法で良いのか、その解答の元となる部分は本文のどこにあり、どうしてそれが解答になり得るのか、
選択式で言えば、どうしてその選択肢が正解で、他の選択肢が間違っているか
そういった根拠となる部分をきちんと説明できるようにならなければ、初見の問題に対する力はつかないと思っています
復習をするときに、解けたということは、ただ正解したということではなく、根拠をもって答えることができた、と考えるべきだと思います。
復習方法に関して疑問を投げかけることで、日々の学習における復習について考え直す契機になればいいなと思い、このブログを書かせてもらいました
暑い日が続きますが、扇風機やクーラーを入れ、水分をしっかりとって、体調を崩さないようにしましょう。