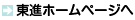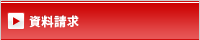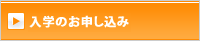ブログ
2022年 4月 11日 私の考える「基礎」固め
はじめまして!早稲田大学商学部4年の稲田です!
さて今年度最初のブログは、僕自身が浪人生として過ごす中で、考えていた、大切にしていた基礎についてのお話をしたいと思います
新宿本科での説明会やホームルームで、「浪人生は現役生と違って、時間があるので、基礎固めに時間をかけてから、過去問に入ることができる」という話を受けました。
僕は現役生の時に、基礎をさぼってしまったという自覚があったので、まず「基礎」とは何かについて考えて、その「基礎」を固めることを、特に重視しました。
「基礎」とは、次のステップに移るために、ここまでは出来ていなければならないというラインのこと、と考えました。「基礎」とは、可変的であり、人やその状況によってさまざまである、と言えるとも思います。そして、過去問に入る段階の「基礎」を「過去問を解ける、あるいは、一発で解けずとも、解答解説を見て、すんなりと理解することができ、その後自身の力で解くことができるだけの学力」と捉えました。
もちろん、入学当初の僕にとっての「基礎」はそこまでレベルの高いものではなかったので、最初の「基礎」を固めて、その次の「基礎」を固め、どんどんとレベルの高い「基礎」に積み上げて、過去問が解ける状態まで「基礎」を固めることを意識して学習を行っていました。
勉強をしていると、目の前にやることが沢山あって、時間が足りないように思えてきたり、焦ってしまったりするかもしれませんが、細分化して、一つずつ完成させていけば、夏までに「基礎」を固めることができると思います。
そのためには考えて学習することが必須です。
今回のブログが、漠然とただ勉強するのではなく、しっかりと考えて勉強をする契機になれば、幸いです
1年間頑張っていきましょう!
2021年 12月 25日 応援を素直に受け取ること
担任助手の砂田です。受験がいよいよ目前に迫りますが、変わらず、落ち着いて勉強できているでしょうか。
いくら受験が近づこうとも、ただひたすらに前進しようとすること。これは試験の一ヶ月前であっても、一週間前であっても、一時間前であっても変わりません。
沢山の努力を積み重ねてきた皆さんにも、今までの軌跡を振り返ると色々なストーリーがあると思います。受験生の皆さんにとってお役に立てる内容となるかは分かりませんが、以下は私が書き残しておきたい大切なストーリーです。
————————————————————————————————–
二年前、センター試験当日の朝、会場の最寄り駅の改札を抜けると、予備校のスタッフや高校の先生と思われる方が激励のためずらりと並んでいます。沢山の声援を受け、緊張と興奮の混ざった気持ちで会場に向かう現役生の中、疎外感を感じつつその列の前を軽く俯きながら歩きます。浪人生は教室で、同じ高校に通う現役生の集団の中ただ一人ぽつんと受験することになると知っていたので、仕方ないとその状況を受け入れたものの、どこか心細さを感じていました。
しかし、ふと先に目をやると、知った顔が見えた気がしました。あれ、と思い近づくと、現役時代お世話になった担任助手三名が校舎の生徒を激励するため立っていたのでした。中学生の頃から私を気にかけ、アドバイスをくれ、頑張った時には褒めてくれた大好きな担任助手の方々でした。
一度受験に失敗してから人と会うことを避け、高校までの人付き合いをすっかり絶ってしまっていた私にとって、とても懐かしい顔ぶれでした。
覚えてくれているか不安に思いつつも前に立つと、担任助手の方々は目を丸くして「うそ、砂田さんだ!」と驚きの声を上げてくれる。そこからは怒涛の勢いで「会えて本当に嬉しい」、「心から応援している」、「あなたを信じてる」、目を見つめ、手を握って、かけがえのない言葉をかけてくれます。忘れないでいてくれたことへの嬉しさ、偶然にも再会できたことのへ感慨、なんとしてでも受からなくてはという昂り、一人静かに勉強し続けてきたその一年で私がこれほど大きな感情の波を感じたのは初めてだったと思います。その時一人の担任助手が、寒いからと言って持たせてくれた小さなカイロが、どれほど暖かかったことか。あまりの嬉しさに、すっかり冷え切って硬くなったそのカイロをお守りのように二次試験まで持って行ったことを覚えています。
そして二次試験本番の朝、また激励の列を尻目に私は会場へ早足で歩きます。高校の同期が”東大生”として激励をする姿を見ることを恐れたのです。ふと名前を呼ばれた気がして振り向くと、そこには現役時代にお世話になった東進の校舎長と担任助手が立っていました。音楽を聞いて集中していた私を、必死に引き留めてくれたようでした。
一年前不合格を確信し、どうしても押さえきれなくて泣いた最後の面談以来、久しぶりに会う校舎長は言葉少なに「頑張ってね」と応援のお菓子を渡してくれます。一年経っても、また同じ場所で待っていてくれている、そんな事実に心が動かされました。
まるで無敵になったような気分で、「絶対に勝てる」そう信じて疑わず、試験は始まりまったのでした。
————————————————————————————————–
私は周りに自分から相談をしたり、アドバイスを求めたりする生徒ではありませんでした。それでも、そばにいてくれた先生、担任助手、そして両親からの応援が、何よりも大きな力、合格への鍵となりました。
「本当に沢山の人が私の合格を願っている。
私は一度皆んなの期待を裏切ってしまったのに、どうしてまた信じてくれるんだろう。」
そんな私のひねくれた気持ちとは裏腹に、無条件に応援し続けてくれた、信じ続けてくれた方々には今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
周りの応援を愛として素直に受け取ること、そしてそれを力に変えること。それが皆さんの合格の鍵になることを期待しています。
2021年 12月 24日 体調が悪い時の勉強法
こんにちは!担任助手の稲田です
だんだんと寒さが厳しくなってきましたね。
受験が近づいていることによるストレスもあって、体調を崩しやすい時期だと思います。
体調管理は非常に重要なことですが、どれだけ気を付けていようが、体調が悪くなってしまうことはあります。
僕は、浪人生のころ、恐らく1週間以上東進を休んだことが、2回ほどありました。
そんな僕の経験を聞いて頂いて、何かの役に立てていただけたらなと思います。
1回目は、11月の中頃に、ウイルス性の胃腸炎にかかりました。
2回目は、センター試験の1週間前ほど前でした。何の病気かは、わかりませんでしたが、直前だったので、最初は本当に焦りました。
高熱が出ることがあっても、丸1日全く勉強をしないというわけにもいきませんよね。
特に2回目のときは、週末にセンターがあるという状態なので、出来る限りのことはしなければなりませんでした。
そんななかで、僕がどのように勉強をしていたかを紹介したいと思います。
まず、体調がましなときは、机がなければできないものをするときだけ、机に向かい、他のものは、できるだけ楽な姿勢で勉強を行っていました。例えば、数学を解くときは、机に向かっていましたが、国語のときは、横になったり、ソファに座ったりして解いていました。
体調が悪化している時は、無理して問題を解くことはせずに、暗記の確認や、解答解説を読む程度にし、頭に入らないだろうなというときは、何もせずに休んでいました。
また、熱があると読んだり、解いたりするスピードが落ちてしまいます。結局本番も完全には、治らなかったのですが、本番も体調が悪いままでも良いように、時間配分には、普段より気をつかいました。
あとは、勉強する時間にも気を付けていました。基本的には普段東進にいる8:30~19:00の間、あまりにも勉強できなかった日は、夕食後に勉強をすることもありましたが、それでも、22時頃までにしていました。今ならできるから、夜遅くまで勉強する、というのは、かえって体調を悪化させることになると考えていたからです。
僕が思うに、体調が悪いなら、治すことを第一としながらも、悪いなりの勉強をすること、そして体調が悪くなっても大丈夫なように普段から勉強しておくこと、この二つが大切です。
今回の話は、あくまで体調を崩した場合です。一番は体調を崩さないことですから、健康管理はしっかりと行って、試験本番まで頑張りましょう!
2021年 12月 13日 【満席締切】東大本番レベル模試 1月最終(1/22.23)
2022年1月22日(土)23日(日)実施[東大本番レベル模試 最終1月]は満席となりました。
申込受付を締め切らせていただきました。
2021年 11月 28日 自信と集中力
こんにちは、担任助手1年の久留です。寒くなってきましたね。
今日は、自信と集中力がこれから入試本番までの鋭い武器になるということを話します。
合格する自信がないときは勉強していても、この勉強で受かるのか、とか、間に合うのか、といった不安で押しつぶされそうになると思います。
ですが、怖くて仕方ないその時、集中できていると思いますか?
するべき勉強を必要なだけ、残りの受験勉強期間でこなしていくためには、不安がっている時間すらもったいないと思いませんか?
時間が少なくなってきたとき、集中するのに必要なのは自信だと私は思っています。
じゃあ自信がない自分には無理だと思った人、自信なんてもともと自分でつけることでしか持てないものです。ここで、私がやっていた自信のつけ方を紹介します。
歩くたびに今日できるようになったことを思い出してください。
歩くたびに、というのは歩く時間という、筆記具をもってガチの勉強をするのが難しい時間の有効活用です。英単語を3個覚えた、計算の時に符号を間違える癖があることを知った、承和の変から安和の変までの流れを覚えた、誤文訂正にかかる時間を8分から6分に短縮するコツをつかんだ、、、
何でも、どんな階層の成長でもいいです。この「思い出し」によって、まず、やってもやっても成長しない自分ではないということがわかると思います。
でもこの「思い出し」の効果はそれだけではありません。思い出すことで、今日の成長が知識系ならその記憶が強化されます。また、何ができるのかということを言語化できるということは、何ができないかということが言語化できるということです。これによって次の勉強のターゲットが絞れます。そして、1番大切なのは、このように「何ができるようになったか」を言語化するためには、「できるようになりたいこと」をできるようにするための目的的な勉強をしなくてはならなくなるということです。「できるようになりたいこと」に一つ一つ戦略を考えてクリアしていけば「できるようになったこと」はどんどん多く、そして質の高い成長になっていくはずです。
このようにして、毎日毎日違う「できるようになったこと」があれば、いつの間にかあれもこれもできる「自信のある自分」になっていると思います。そして、自信があれば集中して質の高い勉強を最速でこなせていけるはずです。このようにして、「集中」と「自信」がうまく循環していけば、「あれもこれも潰してきたから大丈夫」という自信と根拠のある受験生になれます。
今からでは間に合わないんじゃないか、なんて、間に合わないという確固たる理由もないのに不安がっていろんなことを諦めないでください。成長は確実にあるはずなのに無視して、戦う前に戦うことを放棄するのはもったいないです。そして、戦える機会なんて、入試本番の1度きりです。つまり、入試が終わるその時まで根拠なく諦めてはいけないということです。
最後まで読んでくださってありがとうございました。