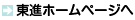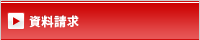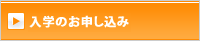ブログ
2022年 7月 13日 過去問を解く上で意識して欲しいこと
こんにちは。早稲田大学国際教養学部4年の三瓶啓吾です。
本格的に暑くなり、夏が始まりましたね。熱中症には注意してください!受験生は特に体調を崩さないことが大前提ですので気を付けてください!
これから、本格的に過去問などの演習に取り組んでいくかと思います。過去問を解き始めるときに意識して欲しいことがあります。
それは基礎基本をメンテナンスするということです。特に私立志望の人に意識して欲しいです。当たり前のように聞こえますができていない人が多いです。
多くの受験生は過去問を通じてその大学の問題構成や出題傾向は理解し、それに伴った対策は行っていると思いますが、基礎基本となると、疎かにしている人は多いのではないのでしょうか。「すでに終わっているからやる必要はない」と思っている人もいるかもしれません。
しかし、その対策の根底にあるのが基礎基本です。基本という土台を定期的にメンテナンスすることが本当に大切です。この土台が固まっていないといくら対策を積み上げても絶対に崩れてしまいます。基礎基本があるから過去問や本番の入試問題が解ける。基礎基本があるから対策が身に付くということを忘れないでください。
必ず過去の授業の復習をしてください。人間は時間が経つと忘れてしまいます。演習に力を入れ始める時期だからこそ、今一度、これを頭にいれておいてください。復習することによって過去問の出来具合も変わってくるかもしれません。これを意識して第一志望合格に向けて走り続けてください!
長くなりましたがここまでお付き合いいただきありがとうございました。
2022年 6月 14日 決して長くない一年
こんにちは。今年も始まってはや2か月が経ちました。毎日があまり変わり映えしない受験生や浪人生にとっては特に気のゆるみやすい時期だと思いますが、1日1日を大切にして着実に1つずつできることを増やしていきましょう!
今回はこの気の緩む時期に喝を入れられるように少し厳しめなことを話そうと思います。
皆さんは数か月前、どんな気持ちで浪人を決めたでしょうか。不合格という結果を突き付けられ、絶望しただろうし、悔しかっただろうし、次は絶対に受かってやる、という気持ちで浪人を決意した人がほとんどだと思います。
たった二ヵ月で、その気持ちを忘れていませんか?
浪人の一年間は、一度突き付けられた現実をひっくり返すには決して長すぎる時間ではありません。てきとうに過ごしていると、何も変わらないままあっという間に一年がたち、去年と同じ結果になるだけです。「浪人したから受かる」ではないのです。
しかし逆に言えば、自分で常に何をすべきか考え、一つ一つ達成しながら成長していけば、この一年間は本当に有意義なものになりえます。この一年間を意味のあるものにするのか無駄にするのかは自分次第です。今気づけたならまだ間に合います。初心を忘れずに、自分が今何をすべきなのかを常に考えながら、受験後に浪人して良かったと心から思えるような一年間にしましょう!!
2022年 6月 7日 浪人生活のモチベーション
こんにちは、千葉大学医学部三年の隅野です。
今回は、浪人時代の1年間、特に前半戦を乗り切るために私が意識していたことについて話したいと思います。
さて、突然ですが、皆さんの今のモチベーションはなんでしょうか?「そんなの、合格以外ないでしょ」って思ったかもしれません。もちろん、最終的にはそうです。では、大学合格だけがモチベーションで、今のこの時期に焦ることができるでしょうか?不安はあっても「このままじゃ受からない、やばい!」といった焦りはあまりないのではないでしょうか。
私は、受験勉強の一番の原動力は焦りだと思っています。不安はじりじりとメンタルをむしばみ、手をとめたくなったり、全部投げ出してしまいたくなることもあるかもしれません。でも、遅刻ぎりぎりで家を飛び出すとき、余計なことを考えたりしないですよね?がむしゃらにダッシュした経験、皆さんも一度はあるのではないかと思います。この焦りをどれだけ維持し続けられるかがつらい受験生活を走り切る大きなカギとなります。
では、合格がモチベーションではないとすると、なにを掲げればいいのでしょうか?テーマは「結果より過程」です。目標は「合格する」「模試で高偏差値をだす」ではだめです。最大限努力しても達成できない可能性がゼロじゃないものを目標にしては、着実なステップアップが見込めませんし、やる気も維持できなくなってしまいます。
そこで、皆さんに意識してほしいのが「〇月〇日までに〇〇を終わらせる」といった課題を自分に課すことです。夏までのこの時期は秋以降の過去問演習に入るために、全教科の基礎力の底上げをして最低限の”道具“を磨かなければいけません。いまの時期に余裕をかましていると、その道具の使い方を訓練するものである過去問演習にいざ入ろうというときに道具が足りず太刀打ちできない、なんてことになってしまいます。余計な不安を吹き飛ばすくらい、自分に課した課題に焦る毎日を送りましょう!
2022年 6月 5日 先に進むために、振り返ろう
こんにちは、担任助手3年生の工藤といいます。今回は、私が浪人し始めた際にしていたことを紹介します。それは、昨年度の自分を振り返ったことです。当時は意図もなく振り返っていましたが、今思うと大変有意義だったと感じます。その意義は2つあると考えています。
1.学習の質の向上につながる
昨年度の自らの行いを顧み、失敗した部分(=合格者と自分との差)やその失敗の原因を把握すると、自分の学習の質を改善させることができます。つまり、失敗の実態が分かれば、対策を練ることができます。そして、その対策を現在の学習にフィードバックできるということです。
また、昨年度の自分を振り返ることで模試後の自己分析の練習にもなります。なぜなら、こうした自己分析と学習状況の改善の作業は、模試後の振り返りとフィードバックという流れにちょうど対応するからです。これから受ける模試に対して、皆さんはこの過程を繰り返して合格者と自分との差を埋めていくので、充実した振り返りを行いたいところです。その第一歩(訓練)として、昨年の自分と向き合うことが役に立ちます。
2.気持ちの整理がつく
浪人したばかりの私は、現役時の自分を振り返る前、意気消沈しており何もする気になれませんでした。しかし、現役時の自身を見つめ直すうちに、気持ちの整理がつき、その後スムーズに計画的な勉強を進められるまでに、精神状態が回復しました。これは私の体験談ですが、皆さんにも言えることのように思えるので書きました。
以上、昨年度の自分を振り返ることの意義を語りました。去年の自分の失敗を見つめるのは辛いかも知れませんが、これをすることによって確実に自分を改善させることができると思います。皆さんの受験生生活もここから再出発する、と言って良いかもしれません。皆さんの受験生としての日々は始まったばかりです。一緒に頑張っていきましょう。
2022年 6月 4日 分野を概観するマップ
こんにちは、東京大学工学部物理工学科三年の砂田です。
受験を終え二年半程経った私ですが、当時から変わらず今も取り入れている勉強法の一つを、今回はお伝えしようと思います。
一言でいうとそれは、ある分野の全体像を概観することです。
理系の方は共感してくれる方も多いと思いますが、どんどん学習内容が難しくなるにつれ、ある現象を説明するために数々の補題の証明が挿入されたり、一旦天下りで直感に反する関係式を受け入れさせられたりということがあります。その現象を理解するのに、直線的なアプローチは不可能で、追加の知識を運用して初めて理解できるということです。目的地にたどり着くため、色々と寄り道をしなければいけません。
先生は生徒が理解しやすいようにと寄り道をさせてくれるわけですが、まだ理解が浅い者にとっては、どうしてその寄り道をしているのか、そもそもその道が本道なのか寄り道なのかという点が分からず、迷子になってしまうことがあります。つまり、次々と出てくる新しい概念を理解するのに必死になるあまり、その知識が導入された意味は何か、そもそも説明したい現象は何だったかという点を見失います。
私はそういったときは決まって、その分野の「マップ」を作ります。まず各章・節を目次のように書き並べて、各項目で語られていることは何かということを、枝葉を削ぎ落として書き込んでいきます。時には図や各概念の関係性も書き加え、その分野の内容をノート1ページ程度にコンパクトにまとめます。出来上がったこのマップは復習時に役立っているのはもちろん、このサマライズする作業自体こそ、その分野の理解への第一歩になっていると私は思うのです。
もちろんこのマップを作っただけでは不十分で、最終的には枝葉一つ一つに注目し、理解を深めていく作業が必要です。しかし、全体像を概観して初めて、その枝葉の学習に意味が生まれるのだと思います。
ある分野の学習を一通り終えたけれど、いまいち理解できた気がしない、人に説明できるほどではないという方は、このような勉強法を取り入れてみてはいかがでしょうか。