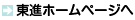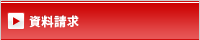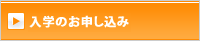ブログ
2022年 7月 18日 「模試」を有効活用していくために
こんにちは。早稲田大学教育学部教育学科1年の村田匠一郎です。
4月から始まった受験生活もスタートから早くも4か月が経とうとしています。勉強の進捗状況は人それぞれだと思いますが、これを読んでくださっている方の多くが、自分の第一志望校・学部学科に合格するという目標から逆算した学習計画を立て、勉強を進めていることを願っています。
今回は、みなさんの中にも既に何回か受けている人もいると思いますが、模試について、私が浪人時代にどのようなものとして捉えていたのかを中心に書いていこうかと思います。
私自身、模試の成績はほとんど気にしていませんでした。というよりも気にしないようにしていました。私は現役時も浪人時も模試で満足のいく成績を取ったことがありませんでした。現役時は悲惨な成績を見るたびに何度と絶望し、そのたびに勉強のモチベーションが下がってしまっていました。
しかし、浪人時には考え方を変え、最優先に考えたのは本番の雰囲気の中で、本番を想定してできるだけ高得点が取れるように精一杯取り組むこと。そして終了後は判定や得点を気にするのではなく、どこが出来て、どこが出来なかったのかの分析をしっかり行うことに重点を置いて、その作業を通じて次の学習に繋げることを意識するようにしました。
そのように取り組んだ結果、普段の勉強にも目的意識をもって取り組めるようになり、模試の結果で明らかになった自分が出来なかった部分を再度復習しなおす作業や、逆にできた部分を応用的な内容を通じて伸ばす作業にとりくむことができました。
模試はあくまでも模試、本番ではない。そういったマインドが、もしかしたら今後も受験勉強を続けていくうえで大事になることがあるかと思います。特に4月から模試を受けているものの成績があまり伸びていないと感じている方は、あえて今は点数や判定のことは忘れて、模試の分析を通して現時点での課題発見や得意分野の向上を第一に考えてみるのもありだと思います。
現役生は夏休みに入り、その多くが受験勉強に本腰を入れ始めます。模試の成績に一喜一憂している時間はありません!より一層身を引き締めて頑張っていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
2022年 7月 17日 モチベーションの高め方
こんにちは担任助手3年の上江洲です。
最近ますます暑くなってきていますが、変わらず勉強できていますか?
今回は僕が受験生時代、モチベーションが落ちてきたときに考えていたことを伝えたいと思います!
それは、最悪を常に考えることです!
つまり、危機感を持ち続けるということです。
これを考える前のモチベーション維持としては、自分が大学生になってることを想像したり、合格をイメージしながら勉強をしていました。
しかし、ポジティブな妄想をしてモチベーションにすることは自分には合っていませんでした。
理由は、想像しただけでそれが実現しているかのように錯覚してしまいうまく作用しなかったからです。
この経験から、逆にネガティブなイメージをしてモチベーションにしようと考えました。
不合格のこと、もう1年浪人することなどを考えました。
結果、危機感がとてつもなく煽られ、いつも以上に勉強に集中することが出来ました。
それから勉強に集中できなくなったときはいつもネガティブなことを考え自分を奮い立たせていました。
皆さんも自分に合ったモチベーションを維持する考えをぜひ見つけてください!その際、参考になれば幸いです。
入試まで先は長いですが、1日を無駄にせずがんばってください。応援してます!
2022年 7月 16日 「バランス」は人それぞれ
こんにちは!担任助手の水口です。
今回は、国公立大学を志望している皆さんに向けて書こうと思います。国公立大学を志望していると、学校の先生や予備校の先生等の周囲の人から「バランスよく勉強しなさい」とアドバイスを受ける機会が多いでしょう。しかし注意が必要です。文字通り、「受験する全科目をバランスよく同じ時間勉強する」、これでは効率の悪い勉強になってしまいます。
私が通っている一橋大学を例に挙げて説明します。社会学部の場合、共通テストの配点割合は英語20 数学20 国語20 地歴20 理科100です。理科は素点がそのまま使われ、理科以外の科目は素点満点200点が20点に圧縮されます。例えば、地歴の2科目目、理科は共に2次試験には無い科目ですが、前者は100点が10点に圧縮、後者は100点がそのまま適用されます。どちらがより入試において重要かといえば、理科になります。一橋大学社会学部を受験する上では、理科の勉強時間を十分に確保する必要があります。
このように国公立大学は科目ごとの配点が異なる場合が多いです。“バランスのよい勉強”とは、この配点の違いを時間配分に反映させた勉強の事です。言ってしまえば、この“バランス”は人によって異なるのです。
また、ゴールを早い時期から認識しておく事も国公立大学合格のためには大切です。合格者平均は何点なのか、その点数を取るには各教科で何点ずつ取る必要があるのか、確認しておきましょう。ただし、合格最低点をゴールにしてはいけません!確実に合格するため、最低でも合格最低点×1,2 、1.3 の得点をゴールに定めましょう。
各教科目標得点が定まれば、大問ごとに取るべき点数も見えてくるはずです!
入試当日、自分は何点取ればよいのか、自分自身の受験勉強のゴールを知ることはとても大切です。もちろん高得点であればあるほど良いことは間違えないし、結果を見てみないとその年の合格基準点が分からないことも事実です。しかし、ゴールが定まらない中、闇雲に勉強することはとても危険です。
勉強効率を上げるために、ゴールから逆算して「今やるべきことをやれているのか」について常に考えていきましょう。やることが多い国公立大学志望者だからこそ、回り道をなるべく避けるため、各勉強の優先順位を定めましょう。
高い壁だと思っていた志望校も、細かくゴールを設定していけば希望が見えてくるはずです。皆さんの受験勉強が充実したものとなることを祈っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
2022年 7月 15日 夏時間の有効活用
こんにちは!担任助手2年の志波です!
毎日暑くて大変ですが、勉強は順調に進んでいるでしょうか。
今回は、夏前から意識して欲しいことを2つ書きたいと思います。
1つ目は、基礎の反復です。
受験生の夏といえば過去問演習!と考える人も多いと思いますが、過去問演習をするに当たってある程度の知識、基礎力が必要です。基礎力や知識がないまま過去問演習に取り組むのは、泳ぎ方を知らないのに海へ飛び込むことと同じと考えることができます。もちろん、1年分だけ早めの時期に解いて、問題を知っておくことは、自分がこれからやらなければいけないことを見据えることが出来るので大切だと思います。しかし、演習はアウトプットにあたるため、ある程度インプットできていない限り、過去問演習をやっても効果が得られにくいといえます。また、基礎は結構やったから大丈夫だと思っていても、何度も繰り返してやらないと、すぐに忘れてしまったり、問題に出てきてもすぐに認識できなかったりします。6月1日の晩御飯は何を食べましたか、と聞かれても答えられない人がほとんどだと思います。このように人間の記憶は、自分が思っているよりも持続しにくいため、適宜チェックする必要があるのです。毎日少しずつでいいので、基礎のインプットや受講の復習などに取り組んでみましょう!
2つ目は、朝から勉強することです。
朝から勉強することのメリットとしては、時間が有効に使えることに加え、暑い夏を乗り切りやすくなることが挙げられます。これは、1日のうち一番暑くなるのは12時~14時頃で、逆に一番涼しいのは早朝や日没後だからです。新宿本科は、7月21日から7:30開館になり、日中も比較的涼しい環境で勉強することが出来ます。この機会を活かして、快適に勉強できたらいいですね!また、入試当日はほとんどが朝から試験が始まると思うので、今のうちに朝から頭が働く習慣をつけてしまいましょう!
何かあれば、担任の先生や担任助手に相談してみてください!
お読みいただきありがとうございました。
2022年 7月 14日 点数=実力?
こんにちは!東京大学理科一類2年の古屋です。
まだ7月序盤だというのにとても暑い日が続いていますね、、!熱中症にならないよう水分塩分はこまめにとり、工夫して暑さを凌ぎましょう!
今回は、模試で「わかっていたのに問題の読み間違えや計算ミスで点数を落とした。本当はもっと高い点数なのに、、」などと思ったことがある人に向けての話をしようと思います。
伝えたいことは大きく分けて2つです。
1つ目は、「確かにそのとおり」だということです。点数=実力ではないことも模試では多いです。計算ミスさえしなければ満点だった問題を、初めから解きなおしたり全てを復習したりすることは優先順位が低く、時間のない時期には無駄にさえもなり得ます。自分がどのくらい出来ていて、どこに時間を費やすべきなのかは、必ずしも点数だけをみて判断すべきではないということです。
2つ目は、「だからと言って放っておくのではなく、きちんと原因を解明し対策を立てるべき」だということです。ケアレスミスをしてしまったから次は気をつけよう!→こんな低い意識では絶対に次も必ずどこかでケアレスミスをします。
①自分のミスのパターンを分析して書き連ね、模試直前に確認するのも1つの手でしょう。前こういう計算でこう間違えたから今回は気を付けようという風に事前に心構えが作れるからです。
②問題を読み間違えて全然違う解答をしてしまう人は、まずは問題文の理解に時間を使い、この解釈以外ありえないなという状況になってから解き始めるなども良いと思います。特に変に問題演習などを積んでしまっていて解法パターンがすっと出て来やすい浪人生などに多いミスでもあります。
③数学においては、1行書くごとに合っているか変なことをしていないか確認をする。というやり方が、僕が先輩から受け継ぎ、僕自身も最良の方法だと考えているものです。1行ごとに確認することでミスに気付く割合が格段にあがります。というかほぼ全てに気付けます。時間はかかりますが本当にミスが減る方法です。
僕もこんな偉そうなことを言っていますが、受験生時代、10月くらいまではケアレスミスのオンパレードでした。直そう直そうと毎回心がけてはいたのに、心がけるだけでは結果は何も変わりませんでした。そんな僕でも上記の方法(特に③)を使ってみてからはミスがほぼなくなり、おそらく本番でも共通、二次ともにケアレスミスは全くしませんでした。ライザップの広告みたいになっていますが真面目に書いています。ケアレスミスの仕方は多様であり、それぞれに対する対処法があると思います。これからまだまだ多くの模試があると思いますが、その1つ1つに対し、ケアレスミスの原因と対策を本気で考え、自分に合う「ケアレスミスを最小限にまで減らす方法」を探し出してほしいと思います。それが模試の大きな意義の1つであると僕は思っています。
応援しています!頑張りましょう!!