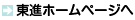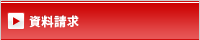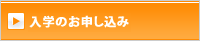ブログ
2022年 6月 2日 意識していたこと
はじめまして、今年から担任助手になりました東京大学理科一類1年の山﨑俊徳と申します。今回は僕が1年の浪人生活の中で特に意識していたことについて、考え方・対人関係の二つに分けて紹介させていただきます。
1.考え方
ここでは一年間の勉強に対する姿勢や考え方について、僕が特に意識していた三つのことをご紹介します。
一つ目は、モチベーション・集中力のコントロールです。現役生と比較してみても、浪人生が勉強に使える時間はとても長く、僕の場合だと2倍くらいはあったように感じます。(勉強の量)だけで学力が伸びると考えれば、浪人生の方が圧倒的に有利に見えますが、実際に東京大学を例に挙げると、現役生と浪人生の合格率にはほとんど差が見られません。これは勉強の量に加えて質が重要な影響を持っているためだと考えられます。大雑把に見積もれば、(勉強の量)×(勉強の質)が学力向上につながると考えてよいでしょう。この(質)を上げるためには、勉強中の集中力・モチベーションを高めることが重要です。具体的に僕がやっていたこととしては、校舎にいるときには勉強だけに集中し、家に帰ったら勉強はせず、趣味や休息に時間をかけるというようにメリハリをつけることや、担任助手の方の話を聞いて大学に入ってからのイメージを持つこと、休みの時間に気分転換として第三外国語や大学範囲の数学物理を勉強してみることなどが挙げられます。
二つ目は、常に目的意識を持つということです。“自分が今何のために勉強していえるのか”を明確にすることで、ゴールから逆算して計画を立て、非効率な学習を避けることができます。具体的には、模試の度に本番を想定して目標を立て、それを達成できるような学習計画を練り、模試の後に反省点を挙げてそれをフィードバックするというサイクルを徹底して行っていました。
三つ目は、自分でコントロールできないことは気にしないということです。受験ではストレス、緊張、体調など様々な要因から影響を受けます。普段の勉強や本番の試験でパフォーマンスを発揮するために、悪影響を取り除くことが重要になります。しかしながら、すべての要因を自分で解決しようとしても、実際には解決できず、それがストレスになってしまいます。そこで、自分に解決できることとできないことを分類し、解決できることのみに対処するという姿勢がとても大事だと思います。
2.対人関係
新宿本科での学習の大半は、講座受講や問題演習などの自習形式のもので、一人で勉強する時間が長かったように感じます。そのような環境の中でも、本科にいる友達や担任助手の方々、先生方や講師の方々との関係は僕にとってかけがえのないものでした。特に個人面談やチームミーティングのときには、先生方や助手の方々が親身になって相談にのり、学習をサポートしてくださりました。また同じクラスの友人とは、わからないところを質問しあったり、模試で競い合って切磋琢磨したりと、いい刺激を与え合うライバル関係を築くことができました。今振り返ってみると、浪人生活では一緒に勉強できる友人関係を築くことはとても大事なことだと思います。
以上二点が、浪人生活の中で僕が特に意識していたことです。あくまで僕個人の例ではありますが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
2022年 6月 1日 現役時に足りなかった2つのポイント
こんにちは。今年から新宿本科校の担任助手となった牧瀬です。昨年一年間この校舎で勉強して東京大学理科一類に合格しました。今年一年間よろしくお願いします。
さて4月から浪人生としての生活が始まって2か月が経ちました。皆さんはどのような姿勢で学習に取り組んでいますか。ここでは参考までに私自身の現役と浪人のときでの勉強を振り返ってみようと思います。
まず現役の頃の私の受験勉強は次のようなものでした。
- 苦手科目・苦手分野だけに偏った勉強
- 模試の結果(判定)に一喜一憂。分野ごとの得点や知識の定着度には目を向けていない。
- 「このままではまずい!」と思い、とにかく問題集を解きまくる。
- 「東大を受けるならこれくらいはできないと」と思い、友達から勧められたレベルの高い参考書に手をつける。なかなか進まず挫折する。
- 簡単な問題でも解くのに時間がかかる。
- 答えを見て「そういうことか」と納得しただけで終わる。解きなおしをしない。
- 反復した回数にだけこだわる。どれだけ定着したかに目を向けていない。
- 自分がミスしやすいポイントをチェックしていない。
- そもそも何ができていて何が出来ていないのか分からない。
この中でいくつかは心当たりのあるものがあったのではないでしょうか。現役の頃はこのような勉強をしていたので、勉強は続けてはいるものの思うように成績が伸びず、ただ挫折感のみが自分の中に残りました。
浪人生としての1年を終えた今、改めて当時のことを振り返ってみると、決定的に足りなかったものが大きく2つありました。それは次のポイントです。
①基礎知識の徹底
②学習を組み立てる力
1つずつ説明していきます。
まずは、①についてです。多くの人にとって今の時期は基礎を固める時期だと思います。レベルの高い大学を目指す人ほど、「これで自分の目指すレベルに届くのか」という不安を抱くかもしれません。しかしどんな応用問題であっても、解くカギになっていることが基本的な知識の理解や考え方にあることは多くあります。また、自分では分かっているつもりでもいざその知識を使おうと思うと使えなかったりすることも多くあります。受講などを通して、これまで分からなかったことを発見し、しっかりと埋めていきましょう。
次に、②についてです。学習を進めていると、自分の立てた計画通りに行かないこともあると思います。また、模試などで自分が思ったように結果が出なかった時には、「今の勉強法でいいのか」という不安がわいてくることもあるかもしれません。現役の頃の自分はただその場の感情にまかせて勉強内容を大きく変えてしまい、結局何も身につかないということを繰り返していました。このような時に大事になってくるのが、自分自身を分析し学習内容に反映させる力です。まず、自分に何ができて何ができないのかをはっきりさせる。次になぜできないのかを客観的に分析し、どのようにすれば解決できるのかを具体的に考える。そして実行に移す。言葉にするとごく当たり前のことのように思えますが、実際にやるとなるとなかなか大変です。どのように計画を立て、実行していくのがよいかは人によっても異なります。ある意味では腰を据えて勉強に取り組める今の時期だからこそ、自分自身にもしっかり向き合っていけるのだと思います。試行錯誤しつつも、自分に合った学習方法を模索していきましょう。
この一年間、私も担任助手として皆さんの学習をサポートしていこうと思います。一緒に頑張りましょう。最後まで読んで下さりありがとうございました。
2022年 5月 31日 1年間意識しなければならないこと
はじめまして。
今年から新しく担任助手になりました、慶應義塾大学 環境情報学部1年の中島沙月です。
大学では建築、デザイン、プログラミングの勉強をしています。私は元々文系でしたが、SFCでは幅広い様々な学問が学べるため、自分が少しでも興味ある分野に手を出し、将来どんな自分になりたいのかを探っています。
さて、今回のブログでは、浪人するにあたって皆さんに考えて欲しい事をお伝えします。
まず、現役の時、なぜ失敗してしまったのかです。一人一人敗因が違うと思います。私の場合は、努力不足ももちろんですが、一番の敗因は自分の学力に対して嘘をつき続けてしまった事です。できない問題をそのままにし、基礎も疎かなのに上ばかりみていて、完全に自分の学力と違う問題に取り組み、なんにも理解していない状態で受験に挑み、ことごとく落ちてしました。
受験勉強するにあたって、常に自分の学力を知り、何が足りていないのか、志望校に向けて何が必要なのかを考え、行動に移していく必要があります。
また、できない事は恥ずかしい事ではありません。むしろ克服しないといけない所を発見できて良かった!とプラスに考えるようにしましょう!
そして、ただ勉強をすればいいのではなく、各教科、各教科の分野で、その勉強はなんのためにやっているのかを考えてみてほしいです。
例をあげると、毎日英単語に触れている人も多いと思いますが、それは読解において単語力が足りていないと思って単語力を身につけるためなのか、1つの単語に対して複数の意味を覚えるためにやっているのか、単語の名詞、形容詞を覚えるために勉強しているのかなど、さまざまな目的が考えられます。
自分はこれが足りていないからこの勉強をしなければならないと1つ1つの勉強に対して、明確な目的をもって勉強をしてほしいです。明確な目的をもって勉強に取り組む事によって、無駄のない効率の良い勉強ができます。
少しでも参考になったら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2022年 5月 30日 素直になること
こんにちは。早稲田大学国際教養学部4年の三瓶啓吾です。現在は絶賛就活中です。
さて、5月ももうすぐ終わります。皆さん、勉強は順調に進んでいますか?第1回目の記述模試も終わりました。時間の流れの早さに驚いている人も多いかと思います。そんな皆さんには浪人1年間を通して意識してほしいことがあります。
それは「素直になること」です。具体的に言うと、取り入れるべき意見や、考え方、勉強法を自分の勉強に落とし込むことです。現役時代、私は、「意味がない」と決めつけて、担任助手の方や、担任の先生が言っていたアドバイスを聞いていませんでした。自分の学習が正しいのかを考えたこともないまま、本番を迎え、惨敗しました。
そこで、浪人するにあたって、今年こそは素直になろうと思いました。チームミーティングで担任助手の先生が言ってくれたことはまず、参考にしてみる。担任の先生に言われたことを頭に入れて計画を立ててみる等、言われたことを一度は試してみることにしました。
しかし、ただ人の意見ばかり聞いて、勉強の仕方が定まらないのは良くありません。闇雲に他人の言う通り勉強していては合格できません。一度参考にしてみて自分に合わなければ、無理に参考にする必要はありません。各自で取捨選択をして、考えながら、自分の勉強方法を確立していくことが重要です。
皆さんの周りにいてアドバイスをしてくれる人は、実際に受かった人、皆さんに受かって欲しいと思っている人です。参考にすべき考えや意見は沢山あります。皆さんも沢山の人の意見を聞き、自分の勉強の仕方をより良いものにしていってください。
残りの期間一緒に頑張りましょう!
2022年 5月 29日 長いようでとても短い
こんにちは。東京工業大学に在籍している担任助手2年の太田です。だんだんと暖かくなり梅雨の走りも見え始めましたが体調にお変わりはないでしょうか。毎日の生活リズムをしっかり整え、きちんとした睡眠をとって万全の状態で勉強に励みましょう。
さて、浪人という期間は(特に初めのほうは)とてもとても長く先の見えない道のように感じますが、ふと気づいたときにはすでに時遅し、あっという間に過ぎ去っていってしまいます。一年という期間は長く感じるかもしれませんが何かをやろうとして計画性をもって実行に移さない限り何も身につかず、ただ無為に時間を過ごすことになるということです。もちろん皆さんは勉強して大学に合格するという使命があるわけですからやること自体はおのずと決まります。では、それに加えてすべきことは何でしょうか。そう、計画を立てることです。先ほどから述べているように一年という時間は限られているため、その枠組みの中で何をするかを明確にしなければいけません。ではどのように計画を立てればよいか少し考えてみることにしましょう。
計画を立てるうえで重要だと私が考えることは次の2点です:
- 明らかに達成不可能な目標はできるだけ立てない。
- 短いスパンの計画と長いスパンの計画を分けて考える。
別に目新しいことではないと思いますが、特に前者についてはとても重要なことのように思います。(あくまで私自身の意見ですが。)なぜならある計画を立てたときに達成できないことが続くと勉強する目的意識や動機付けが薄れていくからです。少なくとも私自身がそうでした。ことに精神的にも健康面でも安定しているとは言えないことが多い浪人生においては、達成するために立てる計画を達成できないことが続けばその分だけ勉強に対する意欲は失われていきやすい傾向があるように思います。そういうわけでより明確で達成するための道筋がはっきりとした計画を立てるために後者の計画を細分化する作業が必要になるわけです。
私自身計画を立てることが得意だったかといわれればどちらかというと不得意の部類であったように思います。もっと言えば計画を立ててもきちんと実行するのが苦手だったのかもしれません。しかし、時には計画を達成できないことがあってもそれはそれでいいと思います。(毎回それでは困りますが。)計画を達成できなかったのなら新しい計画を立てる際に何が足りなかったのかをよく分析して次に生かしていきましょう。そしてひたすらに勉強を頑張ってください。