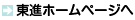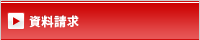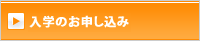ブログ
2022年 10月 3日 勉強の”質”をあげるには
こんにちは。東京大学理科一類1年の山崎俊徳です。
今回のブログは勉強の“質”をテーマに書かせていただきたいと思います。
志望校合格のために必要な実力は “勉強の量×質“ で決まるといってよいでしょう。受験期には前者の量は必然的に確保でき、周りの受験生もそれは同様でしょう。したがって後者の質をいかに上げるかが大きな差を生むといっても過言ではないでしょう。ここでは勉強の質を上げるうえで僕が特に意識していたことを2つご紹介したいと思います。
1つ目は“目的意識を持つ”ということです。目標を定めず闇雲に勉強すると、やる気が出なかったり、効率が悪くなることが多いです。このような事態を避けるためには、目標を明確化し、日々の学習の際に“いま自分は何のために勉強しているのか”という目的意識を持つことが大切です。僕が具体的にやっていたのは、毎週目標を立ててそれの達成のために学習計画を作るということです。こうすることで日々の学習でもモチベーションを維持でき、非効率な勉強を避けることが出来ます。
2つ目は“休憩をうまくとる”ということです。長時間勉強しているとやる気がなくなったり、疲れや眠気に襲われたりすることもあるかと思います。そのようなときには無理をせず休憩を取りましょう。受験期の焦りなどがあると無理に疲れや眠気をこらえて勉強を続けた結果、長時間居眠りをしてしまうということもあるかもしれませんが、この場合は勉強も休憩うまくできず、効率的な時間の使い方ではないように思われます。無理に勉強しようとして1時間うとうとしながら勉強するのと、15分間休憩を取ってから45分間集中して勉強するのとでは違いは明らかでしょう。僕が具体的にやっていたこととしては、出来るだけ時間を決めて休憩時間を学習計画に取り込むこと、眠気や疲れが襲ってきたときは5分間は勉強を続けてみてそれでも集中力が戻らなければ10-20分の休憩を取るということです。気分が乗らないときや体が凝っているときは散歩やストレッチをしてみたり、眠気や疲れを感じた時には仮眠をとるのもよいでしょう。休憩を取る際は必ず時間を決めて、ダラダラしすぎないようメリハリをつけるように注意してください。
以上2点が僕が受験生だった時に勉強の“質”を上げるために行っていたことです。少しでも皆さんの今後の受験勉強の参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
2022年 10月 2日 正解した問題の復習
こんにちは!担任助手4年の稲田です!
暑かった夏も終わり、過ごしやすい季節になりましたね
このぐらいの時期なると、多くの人が演習に取り組む機会が多くなってきているのではないでしょうか
そこで今回は、演習の復習についての話をしたいと思います。
みなさんは演習を行った後、解答を確認して、間違えた問題を解いたり、もう一度通して解いたりするだけで、復習を終わりにしていませんか
実際、自分もそのような方法で行っていた時期もありました。しかし、今はその復習方法で効果的ではないと思っています
間違えてしまった問題に対しては、解けなかった理由を考え、解答、解説、参考書等で確認し、自信をもって解答できるようにする
これはほとんどの人ができていることだと思います
では、正解した問題の復習はきちんと行えていますか
単語や文法などにある、ただ知っているか知らないかを問われているような問題はさておき、根拠をもって解答する必要がある問題を、なんとなくで当ててしまった時、その問題の復習をどのようにしていますか
記述式で言えば、どうしてその解法で良いのか、その解答の元となる部分は本文のどこにあり、どうしてそれが解答になり得るのか、
選択式で言えば、どうしてその選択肢が正解で、他の選択肢が間違っているか
そういった根拠となる部分を説明できるようにならなければ、初見の問題への対応力はついていきません
演習において、解けるということは、ただ正解するということではなく、根拠をもって正解できることであると、考えています
今回は、自分の演習の復習に対する姿勢を紹介することで、今一度日々の学習における復習について考え直す契機になればいいなと思い、このブログを書かせてもらいました
受験本番が近づくにつれて、寒くなっていきますが、続けて体調には気を付けて、学習していきましょう!
2022年 9月 30日 【満席締切】第3回東大本番レベル模試(10/16)
10月16日(日)実施[第3回東大本番レベル模試]は満席となりました。
申込受付を締め切らせていただきました。
2022年 9月 23日 秋以降の短期的なモチベーションの維持について
こんにちは!担任助手4年の志波です!
夏休みが終わり、多くの人は過去問演習を始めたり、基礎の復習を徹底的にやっているのではないかと思います。皆さんは順調に学習を進められていますか?
長い受験生生活の中でモチベーションが定まらない時は少なからずあると思います。
もちろん僕自身も毎日、懸命に勉強していましたがたまにはやる気が全く出ない日もありました。そんな中、少しでもモチベーションを上げて学習することが大事だと思っています。
そこで今回は「短期的なモチベーションの維持」についてお話ししたいと思います!
1.学習項目の細分化
大学受験において一日にやるタスクは膨大なもので取り組むのが億劫になりがちです。
そこでまずはやることを細分化して学習に取り組むハードルを下げることが重要になってきます。人間は初動に一番大きな力を使います。家で寝転んでテレビを見た後に動くのってとても面倒くさいし、やる気が出にくいですよね。これは新しい物事に取り組む際に莫大なエネルギーを消費するのが原因です。その際、未来におけるタスクの量がモチベーションに直接的に影響するため、敢えて少ないと認識することで最初のアクションにスムーズに移行することが出来ます。
(例)
過去問演習→①過去問を解く➁答え合わせ③見直しと過去問分析
文法の復習→①1~4章 時制から仮定法 ➁5章~7章 不定詞から分詞
といったようにやることを細分化し、その達成感を積み重ねていくことで自己肯定感の向上と入試本番における確固たる自信になります。
とにかく良い面が沢山あるのでぜひ試してみてください!
2.趣味や好きなもので息抜きをする
勉強を継続する中でゴールの設定、ご褒美の設定をすることはモチベーションの上昇に良い影響を与えてくれます。そのゴールに向かって自分を駆り立てられる褒美や期間を把握し、学習に対する意欲を高めていきましょう!
例えば好きなテレビ番組が週1回30分であるとすればそれを見ることを目標にタスクを終わらせることを頑張ります。自分がやるべき範囲が終わったらケーキを買うと言ったことでもいいでしょう。コツとしては何点以上という不確定な要素を目標とするより何ページやるといった確実に頑張れば達成できる目標を設定することをおススメします。理由としては頑張れば誰でも達成できるということと自己肯定感を高めやすいということが挙げられます。まずは自分が達成できる数値を設定してコツコツやっていけると非常に良いと思います。
以上のように短期的なモチベーションの上げ方について説明してきましたが長期的なモチベーションを維持するためには結局のところ「志望校に対する熱い思い」だと考えています。
今回はこの要素を前提としてお話しているので短期的、長期的どちらも上手く駆使して有意義な受験生活を送ってほしいと考えています!
2022年 9月 17日 過去問と目的意識
東京大学2年、担任助手の古屋亮です。
もう1年の半分が過ぎようとしていますね。なかなか成績が上がらない人にとってはこの半年はあっという間に思えて、残された半年という短い時間に焦りを感じてしまっているかもしれません。しかし、やるべきこと(あと受験までどれくらい時間があり、自分が受かるには何点とればよいのか、その為に何をどう勉強するべきかを考え、実行すること)はいつになっても変わりません。現役生はもちろん、本科生の皆さんも、きちんと勉強していれば受験当日の朝まで実力は伸び続けます。あせらず自分と向き合いながらコツコツ毎日成長しましょう!
今回は過去問の目的について僕の考えを話したいと思います。
皆さんは何のために過去問を解いていますか?受ける大学の問題傾向、時間配分の目安を知る、今の自分の実力を測るなど色々あると思います。どうせやるのであれば、きちんと目的を意識しながら、自分の実力が最大限あがるように取り組んでほしいので、僕が考え得る過去問を解く目的、意識次第で何が得られるのかを全て書き出してみました。
①問題傾向を把握する
②時間配分の目安を知る
③今の自分の実力を測る
④忘れている知識を確認する
⑤知識を増やす、定石を増やす
①,②→試験本番での立ち回り方を決めるためのものです。問題傾向、時間配分の目安を知り、自分の得意分野苦手分野を考慮して本番での問題を解く順番、時間配分を決めておくことができます。
③.④→これからの勉強方針を決めるためのものです。合格までに何が足りないからどうやって勉強していくのか、残り時間と相談しながら勉強計画を立てる参考にすることができます。
⑤→自分の実力をあげるためのものです。「教科書や参考書、問題集で実力をあげ、過去問でそれを試す」という意見をよく聞きますが、個人的な意見としてはそれには反対です。反対というか、過去問ほど自分の実力をあげるのに適した教材はないと思っています。
過去問というのは、高校生までの全ての勉強の集大成として、色々な知識、考え方を織り交ぜながら、その理解が生徒にあるかを問うために大学の先生方が作られたものです。つまりたった一問に対しても、それを解き、復習することで吸収できる知識や考え方が山ほどあるということなのです。
このように、過去問を解く目的は様々あり、それぞれでその活かし方も変わってきます。ただ闇雲に解きまくるのではなく、自分は何のために解いているのか、これを解き、復習したらどんなことを身につけられるはずなのかをきちんと意識して取り組みましょう!
最後まで読んでくださりありがとうございます、応援しています!