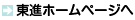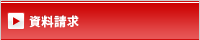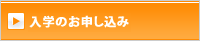ブログ
2023年 10月 10日 さぼることを覚えてしまったあなたへ
こんにちは!担任助手3年の古屋亮です。
肌寒い日増え、秋の訪れを感じている方も多くなってきたのではないでしょうか。色々病気も流行っていますし、気温の変化にもやられないよう、睡眠、食事、休養は欠かさず取り、受験当日まで継続的に勉強を続ける為の体調管理をしっかりと行っていきましょう。
さて、今回は1年の半分が過ぎ去ったこの時期に、成績がちょっと良くなったことによる慢心や、逆にやってもやっても上がらない憤りから、ちょくちょく勉強をさぼることを覚えてしまったあなたに伝えたいことを書いていこうと思います。
大きく分けて、伝えたいことは3つです。
1.本当にもったいない
あなたが4カ月後、第一志望校にあと数点差で落ちてしまった未来を考えてみてください。容易に想像がついてしまうと思いますが、さぼっていた自覚のあるあなたは、きっと自分が嫌になるほど後悔をすることになると思います。さぼってスマホや娯楽に逃げてしまった分勉強していたら受かっていたのではないか。なぜ、あとひと踏ん張りが出来なかったのか、と。
またそれだけではなく、受験のような、人生においてもかなり大きな岐路となるイベントに一年間(やそれ以上)全力で取り組むことができる機会なんてこれからそうそうありません。しんどければしんどいほど、頑張ってこの一年間を全力で乗り越えた時そこから見える景色や感じる達成感は、本当に全力でやった人にしか味わえない最高のものになるはずです。
2.あなただけじゃない
そうは言っても僕らは人間です。もちろんさぼってしまう日がたまにはあるかもしれません。実際、受験生時代の僕もそうでした。ここで言いたいことは、もしあなたがさぼってしまった時に「なんで自分はこんなに頑張れないのか」と自己嫌悪に陥る時間は無駄だということです。あなただけが頑張れないんじゃないんです。皆頑張れない時が少なからずあるのです。なので、あなたがさぼりを自覚した時には、自己嫌悪を抱くことではなく、残された時間で何ができるのかを考えることに時間を使いましょう。
3.変えられるのは今この瞬間から
さぼってしまったと自覚したその瞬間から、やるべきことを始めましょう。人間は過去には戻れませんが未来はいくらでも変えることができます。その時点からの最高到達点に達する為には、自覚をしたその瞬間から全力を尽くして残された時間を有効に使わなければならないのです。
以上3点が今回僕が伝えたかったことです。この話を聞いてどきっとした方も、自分には関係ないと思った方も、精神が不安定になりがちなこれからの時期に、困ったとき思い出せるように頭の隅にでも置いておいてもらえたら幸いです。
あと4か月、一緒に頑張りましょう!!
2023年 10月 9日 復習はどこまで行うべきか
こんにちは!担任助手の稲田です!
夏の暑い日々が終わると、急に気温が下がり、肌寒い季節になりましたね。
このぐらいの時期なると、過去問など、演習に取り組む機会が多くなってきているのではないでしょうか。
そこで今回は、演習の復習についての話をしたいと思います。
みなさんは演習を行った後、解答を確認して、間違えた問題を解いたり、もう一度通して解いたりするだけで、復習を終わりにしていませんか?
実際、自分もそのような方法で行っていた時期もありました。しかし、今はその復習方法で効果的ではないと思っています。
間違えてしまった問題に対しては、解けなかった理由を考え、解答、解説、参考書等で確認し、自信をもって解答できるようにする。
これはほとんどの人ができていることだと思います。
では、正解した問題の復習はきちんと行えていますか?
単語や文法などにある、ただ知っているか知らないかを問われているような問題はさておき、根拠をもって解答する必要がある問題を、なんとなくで当ててしまった時、その問題の復習をどのようにしていますか?
記述式で言えば、どうしてその解法で良いのか、解答の元となる部分は本文のどこにあり、どうしてそれが正答になり得るのか?
選択式で言えば、どうしてその選択肢が正解で、他の選択肢が間違っているか?
そういった根拠となる部分を説明できるようにならなければ、初見の問題への対応力はついていきません。
演習において、解けるということは、ただ正解するということではなく、根拠をもって正解できることであると、考えています。
今回は、自分の演習の復習に対する姿勢を紹介することで、今一度日々の学習における復習について考え直す契機になればいいなと思い、このブログを書かせてもらいました。
急激な気温の変化で体調を崩しやすいので、体調管理をしっかりと行い、学習していきましょう!
2023年 10月 5日 この時期に頑張ることの意義
皆さんこんにちは!担任助手2年の島村駿です。
最近はこれまでの夏の暑さが和らぎ、秋の風が心地よく感じられるようになりました。受験生の皆さんは天気に季節の変化を感じるとともにもうすぐ共通テストであるということを感じてしまうかもしれませんね。
さて、今回はそんな受験も近づいてきた秋のモチベーションの話をしたいと思います。
浪人生にとって「モチベーションの維持」というのは非常に死活問題であると思います。現に私の体験談で言うと、私が浪人していた時に数名の浪人生は徐々に校舎に姿を見せなくなり、勉強しているのかも分からない状態になっていました。自分も無断欠席して、友達と遊んだり、家で勉強すると言いながらもダラダラしてしまう日が何度かありました。
しかし、受験を終えた今言えることが確実に言えることがあります。それは「秋こそが浪人生の本当の分かれ道」ということなのです。夏にだらけてしまったり、モチベーションが上がらないなどあるかもしれませんが、ここからは最後の模試シーズンであり、現役生もしっかりと結果を出してくる頃です。そんな中、自滅してしまうのは非常にもったいないです。
皆がきつい時こそ、いつものルーティン(ちゃんと校舎に来て勉強する、今までの知識を蔑ろにしない、計画的に勉強に取り組む、基礎勉強の復習など)を徹底すれば、自ずと他の人たちと差は開けます。いつものことを淡々とやるだけで他と差を十分につけられるので、今が一番苦しいかもしれませんが、ここを耐え抜いて合格を勝ち取りましょう!!
2023年 10月 2日 秋の過ごし方
こんにちは 担任助手1年の黒田です。
蒸し暑い夏が終わり、乾いた風が心地いい秋が近づいてきましたね。気温が変化する時期ですから体調には気をつけましょう。
さて、今回は秋の過ごし方について話していきたいと思います。
春から夏にかけての学習というのは基本的にインプット、つまり授業が殆どだと思います。新しい知識に触れ、明確に力が上がってくる時期というのは面白く、楽しく受講できた方もいるのではないでしょうか。
しかし、秋から冬にかけてはアウトプットが中心となり、自然と学習は既存の知識を維持する方向性へと変化していきます。その維持を怠って過去問をがむしゃらに解くことは、茎から花をもぎ取って根のないものを土に植えるようとするのと同一です。いくら、その花に水を与えたとしても直ぐに枯れてしまいます。そして、知識というものは吸収することよりも維持することの方が得てして難しく、退屈に感じることも増えるかもしれません。
少なくとも私は秋から冬にかけてが浪人期で一番辛かったです。だからこそ、一日の時間の使い方をより明確に定め、システマチックに復習を行う習慣をつくることで、気持ちでブレることが減り、漫然と勉強をするよりも効率が上がります。
また、授業が終わり始めることで、一日の時間の使い方もよりフレキシブルになります。授業のように1時間半(1時間)という区分けが消滅するため、上記とは別の理由でも、より計画的に勉強を行う必要があります。春と夏にかけて受けた模試やライブ授業での手応えなどから、自分の立ち位置や、どれくらいの時間で集中力が切れるのか、一日のうちでいつ頃が一番捗るのか等を考えて、自分に合った勉強法を確立していきましょう。
これまでの勉強とこれからの勉強は轅と車輪のような関係です。両方を大切にしてこれからも頑張っていきましょう!
2023年 9月 27日 過去問を解いた後こそが一番重要だということ
こんにちは。慶應義塾大学経済学部2年の文川です。
皆さん過去問解いてますか?
思ったより手ごたえがある人。その調子でガンガン突き進んでしまってください。
「こんなのどうやったら解けるようになるんだよ・・・。」などと少しでも嘆く気持ちを抱く人、過去問を一通り解き終えて(当然に)復習も終わった後の行動に志望校攻略のカギは潜んでいるかもしれません。今回は僕が過去問演習後に意識していたことを2つお教えしようと思います。
*このやり方は即効性のあるやり方では断じてなく、塵も積もれば山となるように効果が出てくるものであるということをご了承の上読み進めてください。
一つ目が分析です。
一言でザックリと「分析」といわれるとなんだか拍子抜けした気持ちになるかもしれませんが我慢して読んでください。すごく大事なことです。
(ⅰ)まず自分の取れた点数とその年の平均点、合格者最低点とを比べます。どのくらい差があるのかを考えましょう。
(ⅱ)次にその大学の頻出分野や実際に自分が解いた問題の難易度を考察しましょう。何の分野が出題されどのくらい取れていなければならなかったのかを徹底的に考えましょう。
(ⅲ)それが終わったら自分の取れなかった問題について考えましょう。
このとき、
➀その分野は何で求められていたことは何か
➁時間があったら解けたのか、それとも未知の解法だったので時間関係なく解けなかったのか
③なぜ解けなかったのか
④次に類似問題と遭遇した際に、解けるようであるためには如何にしていればいいのか
を意識しましょう。ここまで出来れば分析編は上出来です。
二つ目が、勉強計画の構築です。
分析して浮き彫りになった課題たちをリストアップし、優先順位をつけていきましょう。この優先順位をつける作業は分析した際に思ったこと(頻出分野や手薄になっていた分野など)をふんだんに加味して行っていきましょう。
あとは実行するだけです。自分で決めた優先順位に従って順々に潰していきましょう。
以上、僕が受験期に演習をした後に行っていた作業ですがどうですか?淡々としていてつまらないと感じたかもしれません。しかしこうした作業を愚直に重ねていくことで暖かい春を迎えるに至るのです。千里の道も一歩から。皆さんの健闘を祈ります。