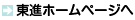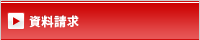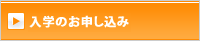ブログ
2023年 11月 25日 やるか、後悔するか
こんにちは。担任助手1年の大島です。
11月も終わりに差し掛かり、受験まで残すところわずかとなりましたね。寒さも一段と厳しくなってきたので、くれぐれも体調管理には気をつけましょう。
みなさんは「あのときああしておけばよかった」、「もっとこうしていれば」と感じたことはありますか?
誰しも一度は経験したことがあると思います。私は学校の定期テストが始まるたびにもっと早くから勉強を始めていればと後悔していました。これを裏付けるように、ボストン大学のリサ・アベンドロフさんが興味深い心理学の研究結果を発表しています。海外旅行に行った旅行者を対象とした研究で、「お土産を買ったとき」と「お土産買わなかったとき」の間でどちらが後悔は大きいかというものです。結果、「お土産を買わなかったとき」の方が、「お土産を買ったとき」に比べ、後悔は大きかったそうです。このように、やらなかった時の後悔は、やったあとの後悔より大きいことが科学的にも証明されています。
これは受験でも同じことが言えると思います。普段の定期テストは学期ごとに実施され、ある程度回数があり修正も利くので後悔はさほど大きくないかもしれませんが、受験は一度きりです。チャンスが少なく、人生を左右するものである分、やらなかった後悔はより大きくなると思います。では、どうすれば「やらなかった後悔」を無くすことができるのでしょうか。
それは、目的を明確化することです。受験であれば、自分のやりたいことを実現するために志望校合格を目指すなど。目的が明確になれば自分が今やるべきことは何かを考え、行動に移しやすくなります。
結果が出なかったら努力しても無駄だという考え方もあると思いますが、私はそうは思いません。例えうまくいかなかったとしても、頑張ったことが経験として残るからです。しかし、何もやらずに終わってしまったら残るのは後悔だけです。
人生は選択の連続です。自分が今どう行動するかで未来は大きく変わります。試験当日、あの時勉強していればと思わないように、最後まで諦めず、一緒に頑張りましょう!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2023年 11月 24日 私が本番に向けて行っていたこと
こんにちは、早稲田大学商学部1年の河﨑樹です。
さっそくですが「本番に向けて行うこと」と聞いてどう思いましたか。
「まさに今本番に向けて勉強してるよ!」「本番に向けて1年、もしくはそれ以上受験勉強に捧げてきてのに、今更これ以上意識することってあるの?」って思った方、何人かいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、本当に本番に向けて行動できていますか。少々細かくはなりますが、今回本番を2度経験した私が本当に有効だと感じたことを説明するので関心のある方は参考程度にご覧いただけると幸いです。
私が本番に向けて行っていたことは「本番のイメージを持って生活を送る」ことです。
本番のイメージとは、受験日当日に行うこと全てを指します。例えば、実際に受験会場で自分が試験を解いている様子や試験の間の休憩時間に行う苦手範囲を確認をする様子、さらに試験会場で昼食を食べる様子などです。
そして、最初に述べた本番のイメージを持って生活を送ることとは、受験当日をイメージし、できる限り現在の生活に当てはめていくことです。
しかし、普段生徒を見ていて気付いたことがあります。それは「受験当日をイメージして行動するなんて模試の日だけ十分だ」という生徒が多いということです。
実際は、模試の日だけでは十分ではありません。そもそも普段から受験当日をイメージして生活をしていないのに、なぜ模試の日に突然受験当日を想定した行動が取れるのでしょうか。模試の時間割に従って行動していれば、受験当日さながらの行動が出来ていると勘違いしがちです。具体的に自分の行動を顧みると、月1回程度の久しぶりの模試で取る受験日を想定した行動では無駄が多かったりするものです。なので、模試当日だけでは不十分だと私は考えます。
最後に、普段から受験日を想定した行動を取ることで、当日どのようなメリットを得られるのか説明したいと思います。普段から受験当日を想定して行動を取っていれば、行動の無駄に気づき、効率化を図ることが出来ます。
例として、試験の間の休憩時間の単語帳の確認を挙げます。短時間で単語帳を確認するために最も効率的な手段は何かを普段から考えて学習に取り組むことで、本番の試験直前で効率よく単語をインプットできます。特に私大における数点の差は非常に重みがあるものです。このように普段から受験当日を想定し行動を取ることで行動の無駄を省き、当日の学習で周囲と差をつけることが出来ます。また普段から受験当日を想定することで想定外のミスを減らすことが出来ます。
昼食を例に挙げます。普段から食後どのぐらいの時間が経てば眠気を感じるのか、どのぐらいの量であれば集中力に支障が出ないのかを考えて日常に反映させていれば、当日食事によって試験に支障が出ることを防ぐことが出来ます。
「昼食は試験に関係ないじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし私は去年食後にデザートと珈琲を摂取したことで血糖値が急上昇して焦燥感を抱き、試験に集中できいなかった経験があります。なので昼食という試験に無関係に感じる場面もしっかり対策することをおすすめします。
以上私が本番に向けて行っていたことです。
ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。少しでも皆さんの役に立てていれば幸いです。皆さんのご健闘お祈りします。頑張ってください!
2023年 10月 15日 一人暮らしをしている方へ
こんにちは!担任助手1年の横山です。
寒暖差が激しくなり、また花粉の季節でもある今は、非常に体調を崩しやすい季節なので、体調管理には気をつけてください。特に睡眠時間を確保することを心がけましょう。
さて今回は、一人暮らしをしながら受験勉強をしている方に向けて伝えようと思います。
それはずばり、
意識的に会話を増やす
ということです。
一人暮らしをしていると、どうしても家族との会話が減ってしまいます。人との会話なんて成績には関係ないと思うかもしれませんが、ずっと誰とも話さずいると、どうしても精神的に辛くなってくることがあります。ある調査によると、コロナ禍で会話の量が減り、およそ半分の人が“ストレスが溜まりやすくなった”と回答しています。ただでさえ受験本番まで残り半年を切り、焦りや不安が募ってくる季節なので、できるだけ精神的な負荷を抑えたいですね。
特に家族との会話を増やすことは、もう一つメリットがあります。それは、家族の不安を和らげることです。ただでさえ辛い受験勉強を、親元を離れてするということは、本人だけでなく家族にとっても非常に大きな選択です。あなたがどのように普段過ごしているのか、何に困っているのか、きっと家族の方は知りたがっているでしょう。できればこれらのことを伝えられると良いですが、なかなか家族に相談しにくい時は、他愛のない話でもいいので、あなたの声を聞かせてあげるとご家族の方は安心されるでしょう。
しかし注意点もあります。それは、ダラダラと喋り続けないことです。皆さんの中には、友達と電話していたら深夜になってしまったという経験のある人もいるでしょう。自由時間で最も大切なことは、休息を取ることです。話しすぎるあまり睡眠時間が削られるようではいけません。そこで私が実際にしていた対策は、話す前に「何時までに終わりたい」と宣言することです。友達と話すことはストレスの解消になり悪いことではありませんが、普段の生活に影響が出ないようにしましょう。
受験勉強で一番大切なのは、“継続”です。本番まで残り半年、なるべくストレスを軽くしながら乗り越えられるようにしていきましょう。応援しています!
2023年 10月 14日 ルーティンをすることの大切さ
こんにちは!早稲田大学教育学部1年の若杉沙羅です。
突然ですが、皆さんは、勉強において毎日必ず行うように決めていることはありますか?
毎日決まったことを行うことをルーティンと言いますが、受験勉強でも、志望校合格のために有効であるため、皆さんにぜひ取り入れてほしいと考えています。
私自身浪人生の時、勉強内容について一番重要視していたのは「ルーティンワークを毎日確実に行えているか、行う時間を確保できているか」ということでした。
そこで今回は、私自身が行っていたルーティンと、その有効性についてお伝えしたいと思います。
まず、私自身が去年1年間行っていたルーティンです。
主に単語や文法などの基礎知識をそれぞれ何ページずつやるのかを、具体的に決めて行っていました。
私が行っていたのは以下の5つです。
①英単語 200単語/もう1種類の単語帳を200単語 計400単語
②英熟語 50個~100個
③英文法、構文 1.5時間
④古文単語 50個
⑤古文文法、漢文句法 テキスト1周/2日
これらを、電車の中やお昼休み、休憩のタイミングに分けて行っていました。
(苦手な英文法、構文は量を決めてしまうとダラダラしてしまうことがあった為、時間で区切ることでメリハリをつけるようにしていました。)
次にルーティンワークが有効な理由は主に二つです。
1つは、基礎知識の定着に向いているということです。基礎知識といえば主に単語や熟語、文法などですが、こういった基本的な部分は、ある程度覚えられていたり、過去問演習に入った後だったりしても、毎日繰り返した方が良いです。ですが、忘れずにやろうと思っていても、ついついやり忘れてしまったり、問題演習よりも単純な作業になるので面倒くさくなって後回しにしてしまったりということも多いのではないでしょうか。
そのため、何をどれだけやるか具体的に決めて固定化してしまうことで継続しやすくなるのです。
二つ目は、精神面でも良い効果があるためです。
まずルーティンワークは、勉強に集中するためのスイッチになります。実際、私はお昼休みなどの休憩を挟むと、なかなか集中しなおすことができず、お昼休憩が過ぎた後もダラダラしてしまっていた時がありました。ですが毎日やっている勉強を行ったことで自然と勉強モードに切り替えることができていました。
勉強の気分じゃない、なんとなくだらけてしまっているといった時には、ルーティンにしていることを実行してみると、自然とスイッチが入ると思います。
また、本番の試験の際には気持ちを落ち着かせるために使うこともできます。いつもと違う環境で大体の人が緊張してしまうと思います。その中で「いつもとおなじことをする」ことで普段の勉強時に近い精神状態に持っていくことができます。
以上が主に私が紹介したいルーティンの効果です。
受験ではあと1点足りなくて志望校に合格できない可能性もあります。そのような厳しい勝負の中で詰めの甘さは命取りになると言えます。そのため、基礎的な知識はなんとなくではなくしっかりと身に着けていってほしいと考えます。また、身に着けた実力を出し切るためにどうしたら実力を最大限発揮できるかを考えていってもらいたいです。
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
2023年 10月 13日 限られた時間を有効に使うために
こんにちは、担任助手2年の牧瀬です。
夏の暑さもこえて、急に秋を感じる時期になりましたね。朝晩冷え込むので、体調管理には気を付けてくださいね。
さて、本番も近づいてきてかなり焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。今回は「時間の使い方」について私の経験も踏まえてお伝え出来たらと思います。
私のことについて話すと、浪人期は「栃木の実家から往復3時間かけて校舎に通う」、という少し特殊な状況で勉強をしていました。他の人と比べても自由に使える時間が短かったのですが、その中で私は次のようなことを意識していました。
1.賢く休憩時間をとる
焦る時期だとは思いますが、パフォーマンスを最大限発揮するためにも適度にリフレッシュすることは不可欠です。とはいえリフレッシュしたらしたで、ダラダラと長引いてしまうことも皆さん経験したことがあるのではないでしょうか。私は長い通学時間をリフレッシュの時間として、本を読んだり音楽を聴いたりすることに使っていました。
そう聞くと「そういうスキマ時間こそ活用すべきなのでは
通学時間をリフレッシュタイムに充てていた最も大きな理由としては「終わりが定まっている」ということでした。終わりが定まっていることでダラダラすることなくリフレッシュすることができていました。皆さんもこんな時期だからこそ、「終わりが定まっている」時間を活用して、賢くリフレッシュしてください。
2.優先順位をつける
この時期になると、「あれもやらないと、これもやらないと」という思いに駆られて、つい手いっぱいになってしまうことも多いのではないでしょうか。そこで重要なのが「優先順位をつけて行動する」ことです。私は毎朝、1日でやるべきこと・やりたいことをリストアップし、それに優先順位をつけてから1日の勉強を始めていました。不安な思いはいろいろあると思いますが、時間は有限です。「自分は何のためにそれをやるのか」よく振り返りながら、今自分に本当に必要なものを見極めてもらえたらと思います。
3.校舎にいる時間に集中する
これは当たり前のことのようで、意外と重要です!よく生徒の話を聞いていると、「帰ったらこれもやって、あれもやって…」という声もたまに耳にします。勉強熱心なのは良いことですが、それ以上に重要なのは校舎にいる時間にどれだけ集中して勉強に取り組めるかです。どれだけ夜、睡眠時間を削って勉強したとしても、結果として校舎にいる時間に集中できなかったら正直もったいないです!先に紹介したリフレッシュにしても優先順位をつけるということに関しても、ここに目的があります。もしかしたら、昼間はあまり集中できないけれど夜になったらスイッチが入るという人もいるかもしれませんが、皆さんが見据える試験本番は昼の時間にあります。生活のバランスが崩れている人は早急に改善して、校舎にいる間にある程度勉強もやりきって、家に帰ったらできる限り早めに休みましょう。
以上、大きく3つのことをお伝えしました。本番まで限られた時間ではありますが、日々完璧ではないにしても、その日にできる最善を尽くして、十分やり切ったと自信を持って本番迎えられるようにしていきましょう!!